データレイクとは?データウェアハウス・データマートとの違いやメリット、データスワンプに陥る原因を徹底解説
最終更新日:2025年11月04日
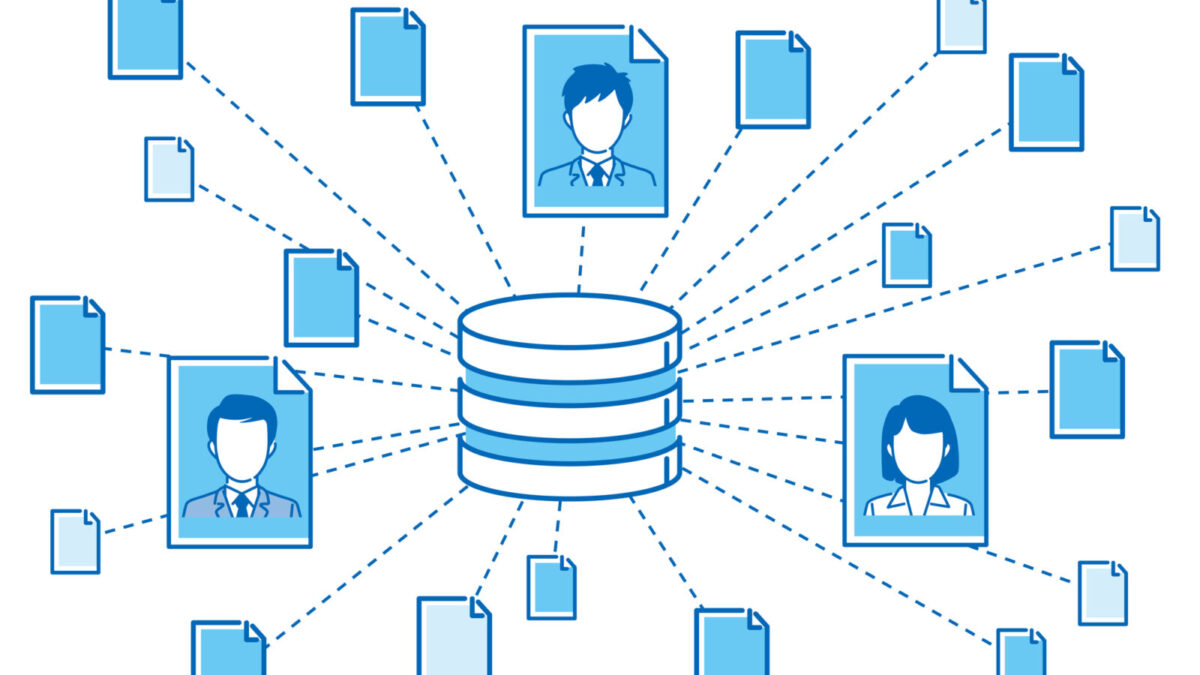
- データレイクは画像やSNS投稿といった「非構造化データ」を含むあらゆる形式のデータを加工しない「生」のまま一元的に保存できるシステム
- データウェアハウスとは異なり、AI開発やデータサイエンスなど、将来の未知の分析ニーズにも柔軟に対応できる
- 導入目的が不明確だったり品質管理を怠ったりすると、活用できないデータが溜まるだけの「データスワンプ(データの沼)」になるリスク
多くの企業が、社内に散在する膨大なデータをAI活用や経営判断に活かしたいが、どこから手をつければいいのか分からないという課題を抱えています。特に、画像やメール本文といった「非構造化データ」は従来のシステムでは管理が困難でした。
データレイクは、構造化・非構造化・半構造化など形式に関係なく、データをそのまま蓄積できるシステムです。取得から活用までのスピードを高めながら、AIによる高度なデータ分析を可能にします。
この記事では、データレイクの基本的な役割から、データウェアハウスとの違い、導入メリット、そして陥りがちな「データの沼」を回避する方法まで、AI時代に必須の知識を分かりやすく解説します。
データ分析に強いAI会社の選定・紹介を行います
今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
完全無料・最短1日でご紹介 データ分析に強いAI会社選定を依頼する
データ分析に強いAI開発会社をご自分で選びたい場合はこちらで特集していますので併せてご覧ください。
目次
データレイクとは?

データレイクとは、構造化データから非構造化データまで、あらゆる形式の情報を一元的に保存できるシステムです。分析するデータを保管する場所として機能するため、格納するデータは加工しない生の形式のままとなります。
構造化データは、形式に従って整理されたデータを指します。データベースや表計算ソフトに格納される、行と列で構成されたデータが典型です。
一方非構造化データは、決まった形式やスキーマを持たず、一定の規則に従っていないデータを指します。具体的な非構造化データとしては、以下が該当します。
- メール本文
- SNS投稿
- 画像
- 音声
- 動画
- センサーログ
非構造化データは情報量が多く、従来のデータベースでは扱いにくいですが、AI学習においては貴重な分析対象となる場合もあります。
近年では、AIを活用した業務自動化やデータ活用が注目されています。データレイクは膨大な社内データを蓄積し、将来的な分析に活かすための基盤として重要性が高まっています。
データ基盤におけるデータレイクの役割
データ基盤において、データレイクは企業内外のデータを一元的に集約し、分析やAI活用の基盤という役割を果たします。
これまでのデータ活用は、整形済みの構造化データが中心でした。しかし、近年は非構造化データの重要性が増しています。データレイクはこれらの情報を形式変換せずに蓄積できるため、多様なデータソースを網羅的に保持することが可能です。
こうして一元化されたデータは、部署を横断して社内の文書やファイルを検索できる「エンタープライズサーチ」の強力な情報源ともなります。
データレイクは「記録のための保存」ではなく、「活用のための蓄積」を実現するシステムとしてデータ基盤において重要な役割を担うのです。
データレイクの主要コンポーネント
データレイクはストレージの一つではなく、データの利活用までを支える機能で構成されています。主なコンポーネントとしては、以下の通りです。
| コンポーネント | 役割 | 主なツール |
|---|---|---|
| ストレージ層 | データの格納 | Amazon S3 Azure Blob Storage Google Cloud Storage |
| データカタログ層 | データの場所、種類、意味などのメタデータを管理 | AWS Glue Data Catalog Azure Data Catalog |
| データ処理・分析層 | 格納されたデータを処理・分析 | Amazon EMR(Spark/Hadoop) Azure Synapse Analytics Google BigQuery |
| セキュリティ・ガバナンス層 | データへのアクセス権限管理や暗号化、監査ログの取得 | AWS Lake Formation Azure Purview |
上記のツールを活用しながらコンポーネントを組み合わせることで、柔軟で拡張性の高いデータレイクが実現されます。
データレイクとAIの親和性
データレイクは、AI開発において極めて高い親和性を持ちます。特に、非構造化データや半構造化データをそのまま蓄積できるため、AIの学習素材として活用し、より高度で複雑な判断が可能なモデル構築が実現します。
従来のデータウェアハウスでは、事前に定義された形式のデータしか格納できず、画像や音声といった非構造化データは管理対象外でした。しかし、データレイクはこれらのデータを元の形式のまま保持できるため、AIが必要とする多種多様なデータを、いつでも取り出して活用することが可能です。
例えば、自然言語処理モデルや画像認識AIでは、膨大な非構造化データが不可欠です。データレイクを活用すれば、こうした多様なデータを前処理の段階から一元管理できるため、AIの開発プロセスが効率化されます。
しかしその一方で、非構造化データはノイズや冗長性を含みやすく、適切な前処理や品質管理が求められます。こうした不確実性、適切な処理・管理が必要となるため、AIとデータレイクを活用するハードルは高いです。
データ分析に強いAI会社の選定・紹介を行います
今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
完全無料・最短1日でご紹介 データ分析に強いAI会社選定を依頼する
データレイクとデータウェアハウス、データマートの比較

データ活用の基盤として注目されるデータレイクですが、似たようなソリューションとしてデータウェアハウスとデータマートがあります。以下では、それぞれの特徴や使い分けについて解説します。
データウェアハウスとの違い
データレイクとデータウェアハウスは、いずれもデータ蓄積と活用を支えるシステムですが、設計思想や用途に違いがあります。
- データウェアハウス:定型的で高速なクエリ処理(経営分析や業務レポート)
- データレイク:自由度の高い分析(AI開発やデータサイエンス)
データウェアハウスは、あらかじめ定義されたスキーマに基づき、構造化されたデータのみを取り扱うことを前提としています。そのため、経営分析や業務レポートなど、定型的で高速なクエリ処理を目的とした利用に適切です。
一方、データレイクはスキーマレスな構造を採用し、非構造化データや半構造化データをそのまま蓄積可能です。そのため、AI開発やデータサイエンスといった自由度の高い分析を必要とする用途に向いています。
データウェアハウスは整備されたデータによる定型業務の高度化に、データレイクは未整備データの柔軟な活用による新たな価値創出に向いていると言えます。
両者は対立するものではなく、連携させてそれぞれの強みを活かす「データレイクハウス」というアーキテクチャも注目されています。
データマートとの違い
データマートは、データウェアハウスの中から特定部門や業務領域に特化したデータ分析を目的とする小規模なデータストアです。営業や経理など利用者ごとに最適化されたデータを格納し、迅速かつ容易に分析できる環境を提供します。
そのため、データマートでは整備された構造化データが前提です。用途が明確な分だけ導入・運用の手間は比較的軽く、特定の業務課題にスピーディーに対応可能です。
一方、データレイクはあらゆる形式のデータを一括して蓄積する広範な格納場所であり、多様なユースケースに対応できる柔軟性があります。明確な目的が定まっていない段階でもデータを取り込めるため、長期的な視点でのデータ利活用に適しています。
用途の違いとしては、以下の通りです。
- データマート:今すぐ使うデータを明確な用途範囲で提供
- データレイク:将来使えるデータを広く蓄積しておく
社内でのデータ活用においては、両者を補完的に活用することで、定型業務と探索的分析の両面に対応できる強固なデータ基盤を構築できます。
データレイクを導入するメリット

データレイクを導入するメリットは以下の通りです。
あらゆるデータの集約
データレイクは、データの形式にとらわれず、構造化・半構造化・非構造化を一括で蓄積可能です。スキーマオンリードの考え方に基づき、データをそのままの状態で蓄積し、必要に応じて後から整形・加工できるように設計されています。
そのため、データ収集時点での選別や変換作業が不要になり、広範な情報を網羅的にストックすることができます。
社内に散在するデータを一元管理することで、サイロ化(データが部署ごとに孤立すること)を防ぎ、組織横断的なデータ活用を促進します。また、蓄積された多様なデータは、AIモデルの学習や複雑な相関分析に活用できる資産となります。
分析精度を向上できる
データレイクを導入することで、分析に使用できるデータの量・種類が飛躍的に増加し、分析の精度向上が期待できます。データレイクでは非構造化データも含めた多様なデータを取り込めるため、見落とされがちだった要因や傾向を検出することが可能です。
例えば、製造現場の異常検知では、機械の振動ログや温度変化、作業者の行動履歴といった非構造化データが業務の効率化のために重要な手がかりとなります。こうした情報を含めて分析を行うことで精緻な予測モデルを構築でき、業務の最適化やトラブル防止につながります。
データレイクは、精度の高いインサイトを引き出すための基盤としても機能し、戦略的なデータ分析を支えます。
データ管理コストを削減できる
データレイクは、従来型のデータ管理に比べて運用・保守のコストを抑えやすい特徴があります。スキーマを事前に定義する必要がないため、データを蓄積する段階での整形・変換にかかる工数を大幅に削減できます。
特に、クラウドベースのデータレイクサービスは従量課金モデルであるため、初期投資や固定費を抑えることも容易です。クラウドストレージの低価格化により、ペタバイト級の膨大なデータを比較的低コストで保管できるようになりました。
データドリブン経営の基盤として機能する
データレイクは、全社的な意思決定をデータに基づいて行う「データドリブン経営」を支える土台として機能します。データを一元的に蓄積・管理することで、組織全体が共通の情報資産にアクセスできるようになり、客観的な判断が可能になります。
データサイエンティストや分析者が加工されていない生データに直接アクセスできるため、既成概念にとらわれない自由な発想でのデータ探索や分析が可能になります。
また、将来的なAI活用や自動化のための学習データとして活用できる点は、データドリブン経営を持続可能な形で推進する上で重要です。常に変化するビジネス環境において、リアルタイムな意思決定を支えます。
データ分析に強いAI会社の選定・紹介を行います
今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
完全無料・最短1日でご紹介 データ分析に強いAI会社選定を依頼する
データレイクが「データスワンプ」に陥る原因
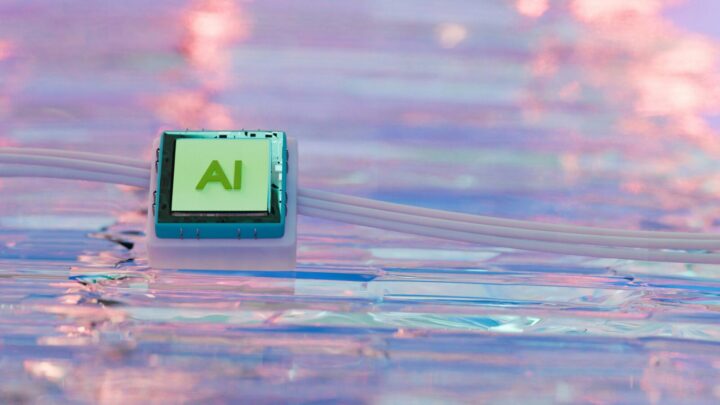
データレイクは柔軟な蓄積が可能な一方で、適切に管理されなければデータスワンプ(使い物にならないデータの沼)と化すリスクがあります。つまり、活用できないデータが蓄積しているだけの状態です。
ここでは、データスワンプに陥る原因と対策を解説します。
目的とユースケースが不明確
データレイクがデータスワンプに陥る要因として、導入時に目的やユースケースが明確でないまま運用を始めることが挙げられます。収集したデータをどのように活用するかの設計がなければ、単なる保管庫にとどまり、価値を引き出すことはできません。
大量のログや非構造化データを無計画に集めた場合、検索性や整合性が失われ、必要なデータを特定するのは困難です。データの存在は把握されていても分析に活かせない状態となり、コストだけが増大する悪循環に陥ります。
そのため、導入前の段階で、以下のように具体的なユースケースを定義することが重要です。
- データを活用・分析するユーザー
- データ活用の対象となる業務
- データの種類
- データの活用目的
目的を明確にした上で、データ構造や収集ルールを整備すれば、データレイクは価値ある資産として機能し続けます。
データの品質管理が不十分
品質管理の欠如も、データレイクがデータスワンプ化する要因として挙げられます。データが無秩序に蓄積されると一貫性や信頼性が損なわれ、データそのものの活用価値が低下します。
例えば、同じ項目でも単位が統一されていなかったり、欠損値や重複データが放置されていたりすると分析結果にバイアスや誤差が生じやすくなります。この問題は、蓄積されるデータが膨大になるほど顕著です。
このようなリスクを避けるには、データの格納時点で品質チェックのルールを設け、定期的なモニタリングと整備が不可欠です。また、メタデータ管理やデータカタログの整備も、品質を可視化・維持に役立ちます。
ガバナンスとアクセス制御の未整備
蓄積されたデータが誰でも自由に書き込み・変更できる状態では、データの真正性や整合性が損なわれやすく、不正確な分析につながる恐れがあります。特に企業規模が大きくなるほど、データ管理は煩雑化します。
また、適切なアクセス制御がなければ、機密情報が共有されるリスクも高まります。こうなってしまうと、内部統制や法令遵守にとどまらず、信頼性のあるデータ活用そのものが困難です。
こうしたリスクを回避するには、組織横断でガバナンスポリシーを策定し、各データセットに対して適切な管理ルールを適用する必要があります。また、AWSやAzureなどのツールを活用すれば、統合的なアクセス制御が可能となり安全で信頼性の高いデータレイク運用を実現できます。
データレイクについてよくある質問まとめ
- データレイクとは何ですか?
データレイクとは、構造化・非構造化・半構造化など形式を問わず、あらゆるデータをそのまま蓄積できる格納システムです。スキーマ定義を事前に行う必要がないためり、保存後に必要に応じて整形・分析ができます。
- データレイクとデータウェアハウスの違いは?
データレイクは形式に依存せず生データを蓄積できるのに対し、データウェアハウスはあらかじめ整形・構造化されたデータを格納することを前提としています。
- データレイク:将来の活用可能性も含めて幅広く活用する基盤、自由度の高い探索的分析やAI開発
- データウェアハウス:明確な用途に最適化された分析環境、定型レポートや高速な集計処理向け
- データマートとデータレイクの違いは何ですか?
データマートとデータレイクの違いは、非構造化データを活用するかどうかです。データマートが特定に業務に特化した小規模なデータ分析環境であるのに対し、データレイクは部門横断的にデータを一括管理できます。
- データマート:短期的・限定的な分析に強い
- データレイク:将来的な活用も見据えた包括的な蓄積に向いている
- データレイクのメリットは?
データレイクのメリットは、あらゆる形式のデータをそのまま蓄積できる柔軟性です。また、スキーマの事前設計が不要なため、収集から活用までのスピードが向上し、分析の効率も高まります。
- データレイクはAIや機械学習とどのように連携できますか?
データレイクは、AIや機械学習の学習データ基盤として非常に相性が良いです。非構造化データもそのまま蓄積できるため、より現実に近いデータでモデルを構築できます。
まとめ
データレイクは、多様な形式のデータを一元的に蓄積し、AI開発や高度な分析を可能にする格納システムです。非構造化データを蓄積できるのが特徴で拡張性・柔軟性を持ちます。
しかし、その導入と運用は単純ではありません。本記事で触れた「データスワンプ」のリスクを回避し、真に価値あるデータ活用を実現するためには明確な目的設定と高度なデータガバナンスが不可欠です。
もし、自社のデータ活用を次のステージに進めたい、あるいはデータレイクの構築を具体的に検討しているものの、何から始めるべきか迷っている場合は専門家の知見を活用することをお勧めします。

AI Market 運営、BizTech株式会社 代表取締役|2021年にサービス提供を開始したAI Marketのコンサルタントとしても、お客様に寄り添いながら、お客様の課題ヒアリングや企業のご紹介を実施しています。これまでにLLM・RAGを始め、画像認識、データ分析等、1,000件を超える様々なAI導入相談に対応。AI Marketの記事では、AIに関する情報をわかりやすくお伝えしています。
AI Market 公式𝕏:@AIMarket_jp
Youtubeチャンネル:@aimarket_channel
TikTok:@aimarket_jp
運営会社:BizTech株式会社
掲載記事に関するご意見・ご相談はこちら:ai-market-contents@biz-t.jp

WEBから無料相談(60秒で完了)
今年度問い合わせ急増中
Warning: foreach() argument must be of type array|object, false given in /home/aimarket/ai-market.jp/public_html/wp-content/themes/aimarket/functions.php on line 1594
Warning: foreach() argument must be of type array|object, false given in /home/aimarket/ai-market.jp/public_html/wp-content/themes/aimarket/functions.php on line 1594
