システムのブラックボックス化とは?原因・AI活用のメリット・ポイントを徹底解説!
最終更新日:2025年08月27日
記事監修者:森下 佳宏|BizTech株式会社 代表取締役
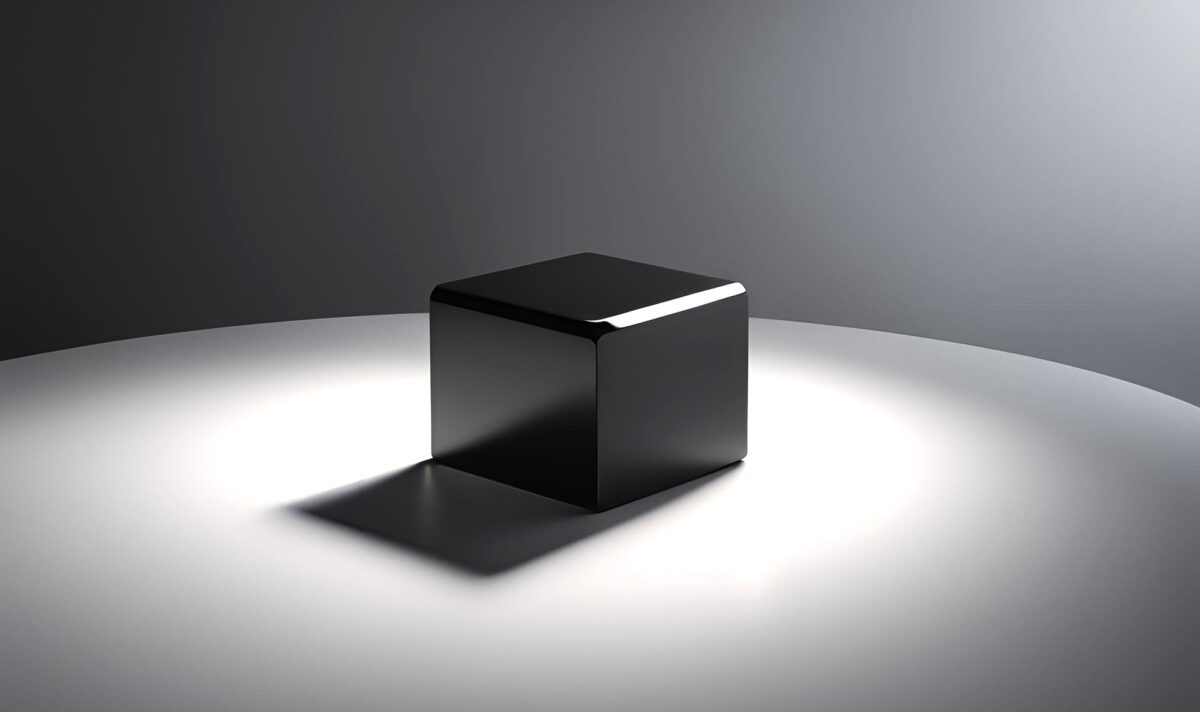
- レガシーシステムのブラックボックス化は事業継続を脅かす
- AIは人手では困難なソースコード解析を自動化し、仕様書の生成やシステム構造の可視化を実現
- AIを有効活用するには、高品質なデータの準備と社内のAIリテラシー向上が不可欠
多くの企業で、COBOLなどで構築されたレガシーシステムがブラックボックス化し、DX推進の足かせとなるだけでなく、事業継続そのものを脅かす「2025年の崖」として迫っています。
しかし、この根深い課題に対し、コード生成・解析AIを活用することで解決の糸口が見えてきました。
本記事では、AIがどのようにしてブラックボックス化したシステムを読み解き、システムの構造を可視化するのかを具体的に解説します。人手では不可能だった現状把握を効率化し、安全なシステム改修やモダナイゼーションへの道を拓くための、実践的なポイントを紹介します。
コード生成・解析に強いAI会社の選定・紹介を行います
今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
・リファクタリング、ソース解析、AI駆動開発等
完全無料・最短1日でご紹介 コード生成・解析に強い会社選定を依頼
目次
システムのブラックボックス化とは?

システムのブラックボックス化とは、システムの仕様や構造、処理内容が社内で十分に把握されておらず、内部の仕組みが不透明な状態を指します。
具体的には、ソースコードの内容や業務フロー、データ連携の詳細が限られた開発者や外部ベンダーしか理解していない状況です。
ブラックボックス化が進んだシステムを放置すると、障害対応や機能追加の際に変更による影響範囲の特定が困難となります。結果として意図しないデグレ(デグレード)を頻発させたり、対応工数そのものを増大させたりして、企業全体の運用リスクを高めます。
コード生成・解析に強いAI会社の選定・紹介を行います
今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
・リファクタリング、ソース解析、AI駆動開発等
完全無料・最短1日でご紹介 コード生成・解析に強い会社選定を依頼
システムのブラックボックス化が進む原因

システムのブラックボックス化は、長年の運用の中で複数の要因が積み重なることで進行します。以下では、代表的な原因を解説します。
Cobolなどの古い言語の使用
COBOLやFORTRANなどのレガシー言語で構築されたシステムは、技術者の高齢化や退職により、対応できる人材が年々減少しています。特に2025年以降、次々と定年退職を迎え、2025年の崖と総務省が指摘する事態を迎えています。
新たなCOBOL技術者の育成も進んでおらず、システムの維持・管理すら困難になる未来が目前に迫っています。
また、長年にわたる場当たり的な改修やパッチ対応が積み重なった結果、処理の整合性や設計の一貫性が失われ、システムが複雑化しています。
これらの要因から、改修や障害対応のたびに特定の技術者に頼らざるを得ず、ブラックボックス化が進行しているシステムも少なくありません。
設計書や仕様書不足
システム開発時に作成された設計書や仕様書は、度重なる改修により実際のシステムと乖離し、陳腐化しているケースも多くあります。また、そもそも過去の開発フェーズで十分なドキュメントが作成されていない場合や、管理が不十分で更新されず放置されている場合も見られます。
こうした状況では、システム全体の構造や機能が可視化されず、担当者間の引き継ぎや保守作業が困難となり、ブラックボックス化が進みます。
担当者の退職・異動による属人化
特定の社員しか分からない業務知識や技術的なノウハウが十分に引き継がれないと、残された社員ではシステムの運用が困難になりがちです。特に文書化やナレッジ共有の文化が乏しい企業では、業務が個々の記憶や経験に依存しやすく、その人物が不在になるとシステムの運用体制が不安定になります。
また、設計意図や処理ロジックが文書化されていないと、改修や障害対応で原因特定が難しくなり、システム管理の属人化がさらに深刻化します。
属人化が進むことで、システム全体の構造や仕様の把握ができなくなり、ブラックボックス化が加速します。
長期運用に伴う複雑化
システムは長年運用される中で、業務要件の変化や新たな機能追加に対応するために、追加開発や改修が繰り返されます。その過程で、当初の設計方針から逸脱したパッチ的な対応や、一時的な仕様変更が積み重なり、構造が次第に複雑化していきます。
その結果、システム全体の構造や処理の流れが把握できなくなり、実装箇所や変更の影響範囲が不明瞭になります。
システムが複雑になると、内部の可視性が失われ、ブラックボックス化が一気に進行します。
外部ベンダーへの依存体制
外部ベンダーにシステムの開発や保守を委託する場合、社内に技術や仕様の知識を蓄積することが困難です。
特に、ベンダーとの情報連携が不十分な場合、仕様変更や不具合対応の履歴が社内で正確に把握できず、社員がシステム全体を把握できなくなることがあります。
外部依存が強まるほどシステムの内在的な知見が失われ、可視化や管理が困難となり、結果としてブラックボックス化が加速します。
システムのブラックボックス化を放置するリスク

ブラックボックス化は、日々の業務で目に見えにくいため軽視されがちですが、実際には企業経営や事業継続に深刻なリスクをもたらします。以下では、代表的なリスクを解説します。
保守・改修が困難になる
ブラックボックス化が進むと、システム内の処理内容や構造が不明瞭になり、保守や改修のたびに事前調査が必要となります。問題箇所の特定に時間と労力がかかるうえに、作業も慎重を要するため、工数が増加します。
その結果、保守・改修コストが膨らみ、開発スピードの低下といった悪循環に陥ります。
システム障害時の復旧遅延
ブラックボックス化が進んだシステムに障害が発生した場合、内部構造が不明瞭ゆえに原因特定に時間がかかり、復旧作業が大幅に遅れます。
特に、業務に直結する基幹システムでは、復旧の遅れが取引先や顧客への影響に直結し、企業の信用失墜や金銭的損失につながります。ブラックボックス化は、緊急時の対応力を著しく損なう要因となるのです。
DX化の阻害
ブラックボックス化したレガシーシステムは、新技術の導入や他システムとの統合を進める際の大きな障壁となります。内部構造や仕様が不明なままでは、API連携やデータ連携の設計が困難になり、想定以上の時間やコストが発生することがあります。
その結果、システム刷新やクラウド移行といったDX推進の重要施策が停滞します。
セキュリティリスク
システム内部のブラックボックスな部分には、脆弱性や不要な処理が潜んでいることも少なくありません。しかし、脆弱性診断を行おうにも、その技術的ハードルが上がり、実質的に診断不可能となっているシステムも少なくありません。
ブラックボックス化が進むと、リスク箇所を把握・監視しにくくなり、外部からの攻撃や内部不正を見逃すリスクが高まります。
特に近年はサイバー攻撃が高度化しており、システムの安全性を評価できない状態は、情報漏えいなど深刻な被害につながりかねません。
コード生成・解析に強いAI会社の選定・紹介を行います
今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
・リファクタリング、ソース解析、AI駆動開発等
完全無料・最短1日でご紹介 コード生成・解析に強い会社選定を依頼
ブラックボックス化したシステムをAIで解消する方法
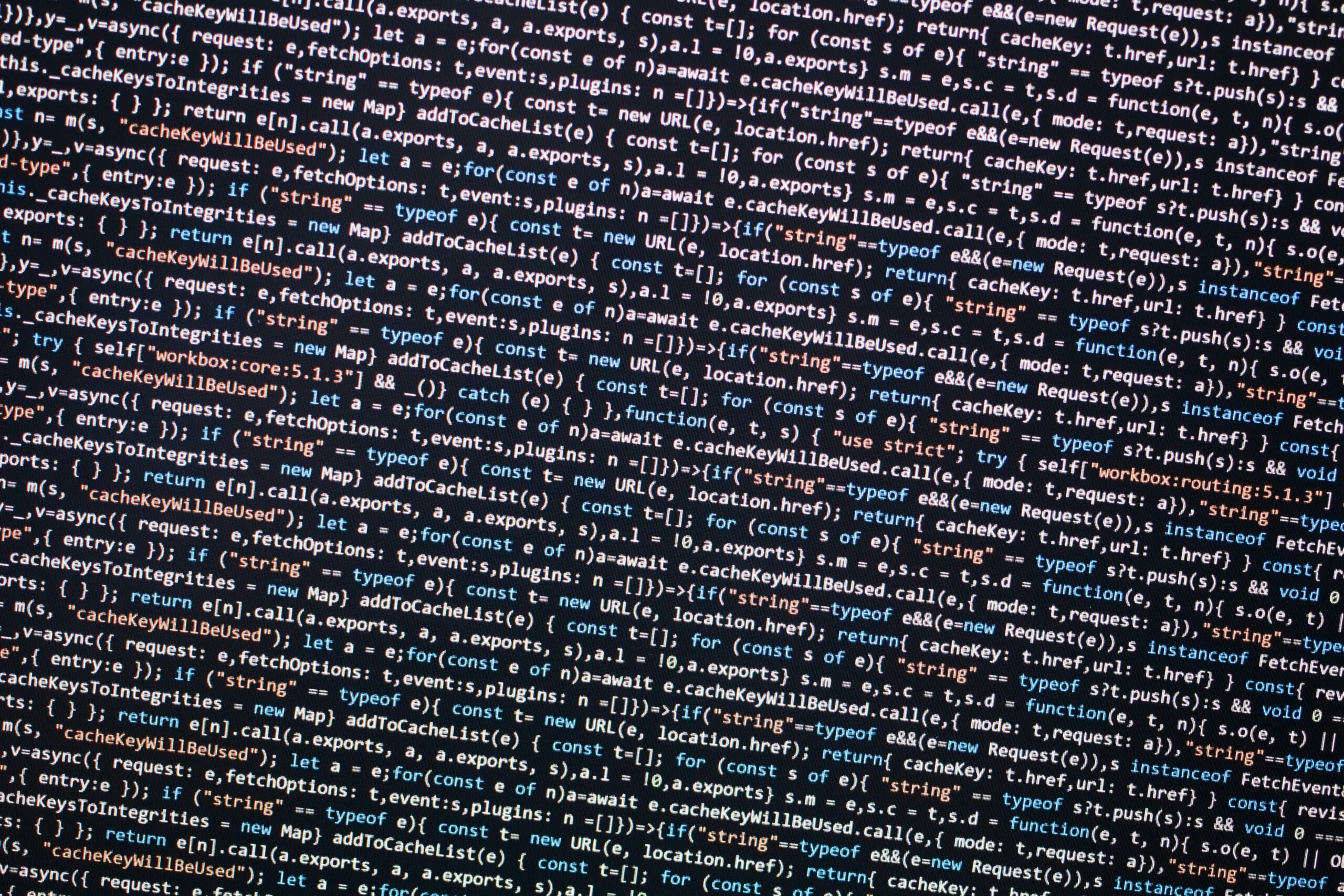
ブラックボックス化を解消するためには、従来の人手による作業では膨大な時間と労力がかかります。そこで近年注目されているのがAIの活用です。
AIを活用することで、ブラックボックス状態から効率良く脱却できます。以下では、ブラックボックス化したシステムをAIで解消する具体的な方法について紹介します。
ソースコード解析によるドキュメント自動生成
システムのブラックボックス化を解消するためには、古くなった仕様書や設計書を見直し、現行システムの状態に即した最新のドキュメントを整備することが重要です。
自然言語処理AI、特にLLM(大規模言語モデル)を活用すれば、過去の仕様書や設計書、ソースコードから重要な要素や変更履歴を抽出し、自動的に要約・整理できます。設計図やソースコードがない状態でも、もとの仕様や仕組みを推定・再構築するリバースエンジニアリングが可能になります。
人手では追いつかない膨大な情報の整備を短期間で推進でき、属人化の解消や引き継ぎの円滑化につなげられます。
ソースコードの解析・可視化
コード生成AIは、ソースコードや設定ファイル、データベーススキーマといった複数の情報源から、システム全体の依存関係やデータフローを解析します。複雑化したシステムでは、モジュール間の関係性や処理の流れを人間が把握するのは困難です。
一方、AI搭載の静的解析ツールを導入することで、「この機能を改修すると、どの部分に影響が及ぶのか」といった影響範囲を瞬時に特定できます。
リファクタリングの実施
コード生成AIがソースコードを静的に解析し、冗長なコード、非効率な処理、潜在的なバグなどを自動で検出します。さらに、より効率的で保守性の高いコードへの修正案(リファクタリング案)を提示することで、開発者を支援可能です。
小規模なリファクタリングを繰り返すことで、既存システムの停止リスクを抑えつつ、ブラックボックス化の解消と保守性の向上を同時に進められます。
また、AIの支援により影響範囲を事前に把握できるため、安全性の高い改修が実現します。
モダナイゼーションの推進
コード生成AIはシステム解析を通じて、古い技術や技術的負債を可視化し、それらを段階的に最新技術へ置き換えるモダナイゼーションを推進します。
クラウド移行やマイクロサービス化、API連携の導入などが代表的な施策で、AIの活用により移行計画の立案や影響範囲の分析を効率化できます。従来のアプローチに比べ、リスクを抑えつつ、持続可能で柔軟性の高いシステム環境への刷新が可能です。
ブラックボックス化したシステムでAIを活かすポイント
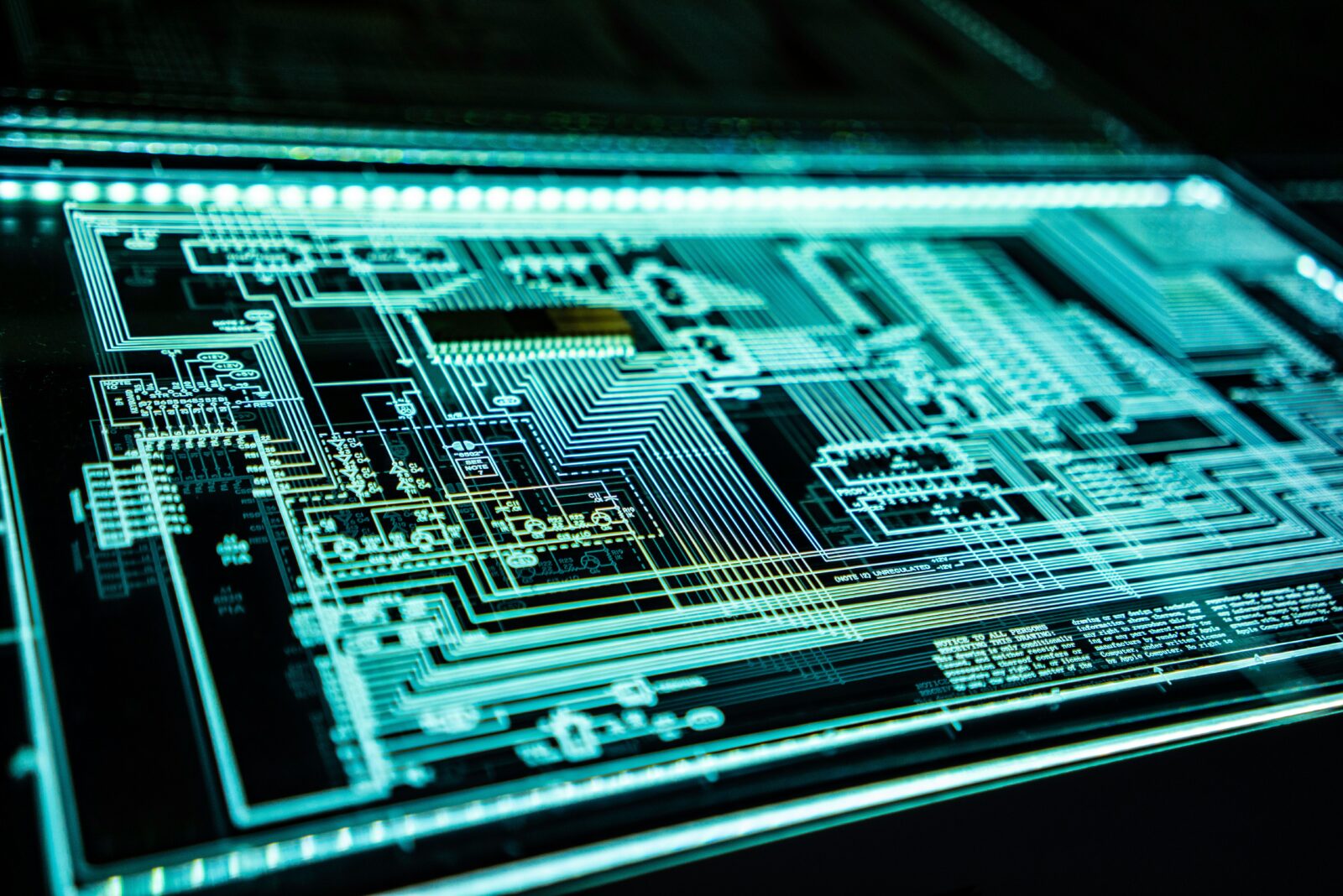
AIを活用してブラックボックス化を解消するには、単にツールを導入するだけでは不十分です。AIの力を最大限引き出し、実効性のある改善につなげるためには、いくつかの重要なポイントがあります。
以下では、AIを活かすためのポイントを紹介します。
高品質なデータを準備する
AIが正確な解析や提案を行うためには、入力データの質が非常に重要です。データが古い場合や欠損が多い・形式が不統一など整備されていない状態では、誤った分析結果を招きかねません。
そのため、AI活用の前提として、ソースコードや設計書、運用ログ、障害履歴などの情報を整理・整備し、最新かつ正確な状態に保つことが不可欠です。高品質なデータを用意することで、AIの分析精度や改善提案の妥当性が高まり、ブラックボックス化の解消につながります。
社内のAI活用リテラシーを底上げする
AIツールを導入しても、現場のメンバーがその仕組みや使い方、出力結果の意味を理解していなければ、十分な活用はできません。AIに対する誤解や過信が原因で、誤った判断や不適切な運用につながるリスクもあります。
そのため、社内研修やワークショップを通じて、AIの基本的な仕組みや活用方法、得られるメリット・限界についての理解を深めることが重要です。現場レベルでのリテラシーを高めることでAIの出力結果を正しく評価・活用できるようになり、組織全体としてのAI活用力が底上げされます。
結果として、ブラックボックス化の解消もより効果的に進められます。
AIの出力結果を人間が確認・解釈する体制をつくる
どれほど高性能なAIでも、提案や回答においてハルシネーションが生じます。ハルシネーションが生じると、誤った仕様理解や不適切な改修方針が導かれ、逆にシステムの混乱やリスクを招く恐れもあります。
そのため、最終的には人間が結果を確認・解釈し、現場の業務やシステム状況と照らし合わせて判断する体制を整える必要があります。AIと人間が役割分担することで、モダナイゼーションを業務に即した安全かつ実効性の高い形で進められます。
コード生成・解析に強いAI会社の選定・紹介を行います
今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
・リファクタリング、ソース解析、AI駆動開発等
完全無料・最短1日でご紹介 コード生成・解析に強い会社選定を依頼
システムのブラックボックス化についてよくある質問まとめ
- システムのブラックボックス化とは何ですか?
システムの仕様や内部構造、処理内容が社内で十分に把握されておらず、不透明になっている状態を指します。ソースコードやデータ連携の詳細が、限られた担当者しか理解していない状況などがこれにあたります。
- ブラックボックス化を防ぐには、どのような対策が有効ですか?
設計書や仕様書の継続的な整備、ナレッジ共有の仕組みづくり、属人化を避ける体制構築が重要です。
また、AIを活用して定期的にシステム構造を可視化・点検することも、予防策として有効です。
- なぜシステムのブラックボックス化は進んでしまうのですか?
主な原因は以下の通りです。
- 古い言語の使用: COBOLなど、対応できる技術者が減少している言語で構築されている。
- ドキュメント不足: 設計書や仕様書が更新されず、実態と乖離している。
- 属人化: 担当者の退職や異動により、知識が引き継がれない。
- システムの複雑化: 長年の改修の積み重ねで、構造が複雑になっている。
- 外部ベンダーへの依存: 社内に技術的な知見が蓄積されない。
- AIを使って、どのようにブラックボックス化したシステムを解消できるのですか?
AIは以下の方法でブラックボックス化の解消を支援します。
- ドキュメント自動生成: ソースコードを解析し、仕様書や設計書を自動で作成します。
- 構造の可視化: システム全体の依存関係やデータフローを解析し、改修時の影響範囲を特定します。
- リファクタリング支援: 非効率なコードや潜在的なバグを検出し、修正案を提示します。
- モダナイゼーション推進: 最新技術への移行計画の立案や影響分析を効率化します。
まとめ
システムのブラックボックス化は、古い開発言語の使用や設属人化などが主な原因であり、放置すると障害復旧の遅延やセキュリティリスクの増大といった深刻な問題を引き起こします。
ブラックボックス化の解消に、近年注目されているのがAIの活用です。AIはリファクタリング提案やモダナイゼーション推進に役立ち、従来人手では膨大な工数が必要だった可視化・改善作業を大幅に効率化できます。
この機会にAIを活用し、自社システムを改修しましょう。

AI Market 運営、BizTech株式会社 代表取締役|2021年にサービス提供を開始したAI Marketのコンサルタントとしても、お客様に寄り添いながら、お客様の課題ヒアリングや企業のご紹介を実施しています。これまでにLLM・RAGを始め、画像認識、データ分析等、1,000件を超える様々なAI導入相談に対応。AI Marketの記事では、AIに関する情報をわかりやすくお伝えしています。
AI Market 公式𝕏:@AIMarket_jp
Youtubeチャンネル:@aimarket_channel
TikTok:@aimarket_jp
運営会社:BizTech株式会社
掲載記事に関するご意見・ご相談はこちら:ai-market-contents@biz-t.jp

