データ基盤とは?構造や企業で活用するメリット、構築手順、ポイントまでを徹底解説!
最終更新日:2025年11月04日
記事監修者:森下 佳宏|BizTech株式会社 代表取締役

- データ基盤は、社内に散らばるデータを一元化し、いつでも使える状態に整えることでAI活用やデータに基づく迅速な意思決定を可能にするための土台
- データ基盤は、データの「収集」「蓄積(データレイク)」「加工(データウェアハウス)」「分析(データマート)」といった階層構造
- データ基盤の構築を成功させる鍵は、導入目的を明確にし、特定の部門や課題から小さく始める「スモールスタート」で実績を積みながら、将来の拡張性やデータ管理のルール(ガバナンス)も視野に入れて段階的に進める
DXやAI活用の重要性は理解しつつも、「社内のデータが部署ごとにバラバラで、有効活用できていない」課題を感じている企業が多いようです。こうした悩みを解決し、企業の競争力を高める鍵となるのがデータ基盤です。
データ基盤を導入することで、情報の一元管理が可能になり、分析にかかる時間の短縮、部門間の連携強化、そしてデータ分析AIとの連携による高度な予測や最適化が実現できます。
この記事では、データ基盤とは何かという基本的な概念から、その構造、導入メリット、具体的な構築手順、そして自社に最適化するためのポイントまでをわかりやすく解説します。
データ分析に強いAI会社の選定・紹介を行います
今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
完全無料・最短1日でご紹介 データ分析に強いAI会社選定を依頼する
データ分析に強いAI開発会社をご自分で選びたい場合はこちらで特集していますので併せてご覧ください。
目次
データ基盤とは?

データ基盤とは、企業が保有する多種多様な情報を一元的に蓄積・管理・活用するシステムを指します。データの収集・保存・整備・分析・可視化できるようにするための一連の仕組みを包括する概念です。
単なるストレージではなく、蓄積したデータを加工・分析しやすい形に整える処理機能が含まれており、データドリブンな組織づくりを支えます。
従来、企業のデータは営業、マーケティング、開発といった各部門のシステム内に個別に保存・管理される「サイロ化」の状態にありました。これでは、部門を横断したデータ活用ができず全社的な視点での迅速な意思決定は困難です。
データ基盤は単なる情報の保管場所ではなく、企業が高度なデータ戦略を推進する上での土台となるツールです。
企業でのデータ活用におけるデータ基盤の役割
企業がデータを活用して意思決定を行うには、正確で信頼性のある情報を取得できる環境が必要です。そこで中心的な役割を果たすのが、データ基盤です。
データ基盤が整備されることで、具体的には以下のようなことが可能になります。
- 社内外のデータの統合
- データ品質の向上
- 迅速なデータ活用
部門ごとに分散していたデータを統合し、全社的に一貫性のある情報基盤を整えることで、経営層から現場まで共通のデータに基づいた判断が可能になります。
また、データの整形や分類、必要な形式への変換を自動で行う機能も備えています。従来は時間や手間のかかっていた集計・分析業務が効率化され、人的リソースの戦略的な再配分が可能です。
さらに、組織内でのデータ共有が容易になることで、部門横断の連携も促進されます。
例えば製造業のデータ分析・活用では、品質管理システムの不良品データと、生産実行システムの製造実績データ、さらに設備のセンサーデータを連携させることが可能です。これにより、特定の不良品が「どの機械で、いつ、どのような条件下で」製造されたかを迅速に特定し、根本原因の究V明に繋げられます。
AIとの関係性
AIは学習と推論を通じてパターンを見出し、予測・分類を行いますが、精度と信頼性は元となるデータの質と量に大きく依存します。つまり、データ基盤が整っていない状態では、AIの導入効果も限定的になってしまうのです。
データ基盤は、AIに必要なデータを一元的に管理・提供する機能を持っています。データ基盤に集約されたデータによって、AIは全社的な文脈を踏まえた分析や予測を実行できます。
また、データの前処理を自動化する機能によりクリーニングや変換作業の負担も軽減され、スムーズにデータを活用できます。
このように、データ基盤はAIが学習する情報を管理するシステムであり、AIの導入・活用においては欠かせません。
データ分析に強いAI会社の選定・紹介を行います
今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
完全無料・最短1日でご紹介 データ分析に強いAI会社選定を依頼する
データ基盤の構造

データ基盤は、データ収集から始まり、蓄積・加工・分析という主要機能を軸に構成されています。それぞれの段階で異なる技術が用いられ、役割も明確に分かれています。
データソース
データの発生源からデータ基盤は始まります。以下のような社内外のあらゆるデータソースを含みます。
- CRM
- SFA
- MAツール
- ERP(基幹システム)
- Webサイトのアクセスログ
- IoTデバイスのセンサーデータ
- SNSデータ
関連記事:「データ収集とは?AI開発に重要な理由・具体的な収集方法や収集のコツ・種類や手法」
蓄積(データレイク)
データレイクとは、構造化データ、非構造化データ、半構造化データを含めて、あらゆる形式のデータを保存できるストレージ領域です。
データレイクは前処理を施す前の状態で保存できるため、取り込みの柔軟性が高く、リアルタイム性に優れています。IoT機器やセンサー、ログデータ、音声・画像ファイルといった多様なソースから得られるデータを、スピーディーに収集できます。
AI活用を視野に入れる場合には、学習に必要なデータ量が膨大になるため、保存先の柔軟性とスケーラビリティが求められます。その点、データレイクはクラウドベースの運用とも相性が良く、データ容量の拡張にも対応しやすいため将来的なAI活用に向けた土台として有効です。
加工(データウェアハウス)
データウェアハウスは、データレイクに蓄積されたデータを整理・変換し、分析や活用に適した構造へと整える役割を果たします。
データウェアハウスでは、各種データソースから収集した情報をETL(抽出・変換・格納)プロセスにより加工し、スキーマに基づいて統一された形式に整えます。これにより、データの粒度やフォーマットが統合され、全社的に一貫した分析が可能です。
また、高速なクエリ処理性能を備えているため、大量のデータでも短時間で検索や集計ができます。AI導入においても、前処理が適切に施されたデータを供給することは、学習精度や結果の信頼性に直結します。
関連記事:「データプレパレーションとは?AIにも重要!」
分析(データマート)
データマートとは、特定の部門・業務に特化した形で、データウェアハウスから必要な情報を抽出・整理して提供するシステムです。利用者にとって扱いやすく、即時性の高いデータ活用を実現します。
データウェアハウスが全社的な統合データを対象とするのに対し、データマートは部門別に特化し、業務で求められるKPIや指標を把握できるように最適化されています。そのため、現場の担当者が専門的な知識を持たなくても、必要なデータに素早くアクセスし、分析を進めることが可能です。
さらに、データマートによって組織内のデータ利活用が促進され、分析結果に基づくアクションをスピーディーに行えます。AIやBIツールとの連携も容易で、より高度な予測や意思決定を支援します。
データマートは、データ基盤全体の最終出口として、業務に直結する情報を提供する要素です。
データ基盤を導入するメリット
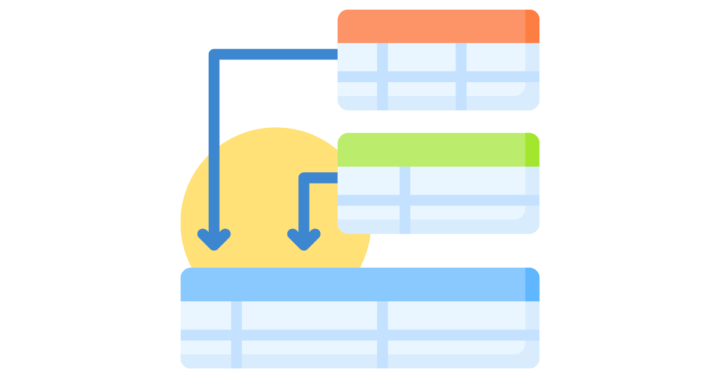
データ基盤を社内の情報管理システムに採用することで、以下のようなメリットが期待できます。
データの一元管理による業務を効率化できる
データ基盤は、企業内に散在していた情報を一元的に管理できます。データの収集、加工、分析といった一連のプロセスが自動化・効率化され、これまで手作業で行っていた多くの時間を削減可能です。
複数のシステム間でデータの整合性を保つ必要がなくなり、日常業務の処理時間が短縮されます。これにより、従業員はより創造的な業務に集中できるようになり、組織全体の生産性が向上します。
データドリブンな意思決定の実現
経営層は信頼性の高い集約データをもとに、データドリブンで迅速な意思決定を下すことが可能です。売上動向、顧客行動、在庫状況などを多角的に分析することで、より精度の高い経営判断や戦略立案が実現します。
また、リアルタイムで更新される情報に基づいて業務を進められるため、タイムラグによる判断の誤りも減少します。さらに、データの所在が明確になることで、情報セキュリティやガバナンスの強化にもつながります。
データの分析速度を向上できる
データ基盤の導入によって、統合された基盤上で自動的に処理されるようになり、企業内でのデータ分析速度を大幅に短縮することが可能です。ETL(抽出・変換・格納)処理が標準化されることで、分析前の準備工程が簡素化されます。
また、データウェアハウスやデータマートを活用することで、クエリ実行時の応答速度も向上します。大量データに対する検索・集計処理が効率化され、必要な情報を即座に可視化できる環境が整います。
業務の属人化解消
データ分析のプロセスが標準化されることで、特定の担当者に依存することなく誰もがデータに基づいた分析を行えるようになります。これにより、担当者の異動や退職によるリスクを低減し、組織としてのデータ活用能力を底上げできます。
自社専用のAIシステム開発へ活用できる
データ基盤は、自社専用のAIシステムを開発・運用するためのインフラとしても機能します。社内に蓄積された実績データや業務ログを体系的に収集・整理できるデータ基盤があれば、自社の業務に特化したAIモデルを効率的に構築することが可能です。
自社業務に応じたAIシステムを内製化できれば、汎用的なツールでは得られない高い業務適合性や独自性を実現可能です。製造業であれば設備保全の最適化、流通業であれば需要予測の高度化など、実用性の高いAI導入が進めやすくなります。
データ分析に強いAI会社の選定・紹介を行います
今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
完全無料・最短1日でご紹介 データ分析に強いAI会社選定を依頼する
データ基盤の構築手順

データ基盤の構築は、以下の手順で進めるのが基本です。
- 導入目的の明確化
- 要件定義・スケジューリング
- 設計
- 開発
- 運用・改善
それぞれの手順について解説していきます。
導入目的の明確化
データ基盤の構築を始めるにあたってまず行うべきことは、導入目的の明確化です。目的が曖昧なままではシステムの設計方針が定まらず、導入後に期待する効果が得られないリスクが高まります。
具体的には、以下のような業務課題・経営目標に直結した導入理由を定義する必要があります。
- 営業データを一元管理して売上分析を迅速化したい
- 部門間の連携を強化したい
- 業務を効率化したい
- データドリブンの意思決定を強化したい
これにより、関係者間での認識のずれを防ぎ、プロジェクト全体の方向性を統一できます。
目的を明確にすることで、必要なデータの種類や量、求められる処理スピード、連携すべき既存システムなどが見えてきます。
要件定義・スケジューリング
データ基盤の導入目的が明確になった後は、具体的な要件定義とスケジューリングを行います。要件定義では、以下のような要件を洗い出し、技術的・業務的な観点から必要条件を整理します。
- 実現したい機能
- 処理能力
- 取り扱うデータの種類
- データの更新頻度
- セキュリティ
- 連携システム
これにより、設計工程での仕様のブレや、追加コストの発生を抑えることが可能です。
また、スケジューリングも重要な作業の一つです。データ基盤の構築には複数の工程があるため、フェーズごとの作業内容と期間を明確にし、進捗管理しやすい体制を整えることが求められます。
設計
要件定義とスケジュールが整った後は、それに基づいてデータ基盤の設計を行います。設計のフェーズでは、以下の要素を明確に定め、実装に向けた具体的な技術仕様を策定します。
- クラウドか、オンプレミスか
- 保存形式
- 処理の方式
- システム構成
設計が曖昧なままだと、開発段階でのトラブルや再設計の発生につながり、プロジェクト全体の遅延や品質低下を招く恐れがあります。
特に重要なのは、データフローの設計です。どのデータを、どのタイミングで、どのような形式で取り込み、どの処理を経て保存・分析するのかを定めることで基盤全体の構造が明確になります。
また、ストレージやサーバー、クラウドサービスなどインフラの選定も含めたアーキテクチャ設計も必要です。どの製品・サービス(AWS, Google Cloud, Snowflake, Tableauなど)を利用するのかを要件や予算、将来性に合わせて選定します。
開発
設計フェーズで定義した内容をもとに、データ基盤の開発に移行します。この段階では、以下のような実運用に向けた具体的なシステム開発を行います。
- 各種データの取り込み処理
- 蓄積先となるデータレイクやデータウェアハウスの構築
- 必要な加工処理の実装
- BIツールやAIシステムとの連携
開発では複数の技術領域が関係するため、データエンジニアやシステムエンジニアなど役割ごとの連携が欠かせません。また、構築したシステムが業務要件を正確に満たしているかを確認するための、単体テストや統合テストも並行して実施されます。
開発が完了した後には、ステージング環境での検証を行うのが一般的です。いきなり実用ではなく、段階的な進行により、リスクを抑えつつ安定した運用体制を築くことが可能となります。
運用・改善
データ基盤の構築が完了した後は、データの取り込みや更新が正しく行われているか、分析環境が安定して稼働しているかを監視し、異常があれば迅速に対処できる体制を整えます。
また、ユーザーからのフィードバックを反映し、UIの改善やクエリ処理の高速化といった利便性向上の取り組みも必要です。
運用にあたっては、ビジネス環境や社内ニーズの変化に応じて、データソースの追加や分析対象の拡張が必要になるケースもあります。継続的なモニタリングを通じて、段階的に基盤を改善・拡張していくことが重要です。
自社に最適なデータ基盤を構築する4つのポイント
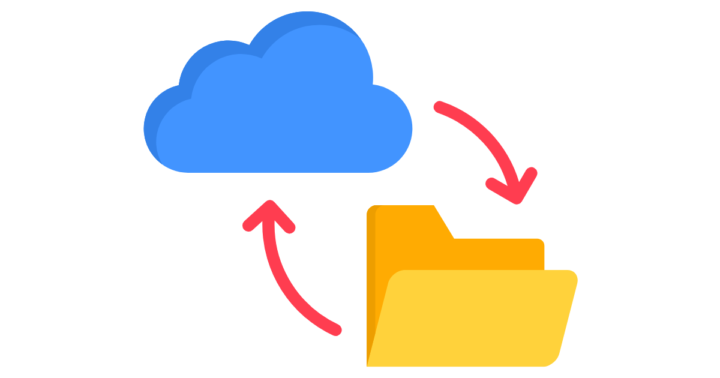
データ基盤はただ構築するだけでは、効果が見込めません。「自社に最適な」データ基盤を構築するには、以下のポイントが重要になります。
適切な構築形態を選択する
自社に最適なデータ基盤を構築する上では、構築形態の選択が重要です。データ基盤は、大きく分けて以下の3つの構成を取るのが一般的であり、それぞれに特徴と適合性があります。
- オンプレミス型:自社内にサーバーやストレージを設置する方式。セキュリティや制御性に優れる一方、初期投資や保守運用の負担が大きい
- クラウド型:柔軟なスケーラビリティやコストの平準化が可能で、短期間での導入や変化への対応に適している
- ハイブリッド型:基幹業務はオンプレミスで管理し、分析・AI学習にはクラウドを活用する方式
AI活用を前提とする場合、クラウド型のデータ基盤は、計算リソースや外部サービスとの連携が強みとなります。クラウドサービスは拡張性(スケーラビリティ)が高く、将来的なデータ量の増加や、新たな分析ツールの導入にも柔軟に対応可能です。
一方で、社内情報の流入を懸念する場合は、オンプレミス型が適切です。
構築形態を選択する際は、中長期的な視点での運用コストや拡張性も考慮しながら、バランスの取れた形態を選定することが重要です。
スモールスタート・段階的拡張
データ基盤の導入においては、最初からすべての機能を一度に整備しようとするのではなく、スモールスタートで進めるのがポイントです。初期段階で過度な機能を盛り込むと開発が複雑化し、費用やスケジュールが膨らむリスクが高まります。
まずは限られた用途や部門に絞って導入し、実績を積みながら段階的に拡張していくことが現実的です。例えば、特定の業務のデータ可視化やレポート自動化など、比較的導入効果が見えやすい分野から着手することで現場の理解と協力も得やすくなります。
その上で、利用実績やフィードバックを基に改善を重ね、他部門や新たなデータソースへと対応範囲を広げていきます。
他にもスモールスタートには、失敗時のリスクを最小限に抑えられるメリットもあります。小規模な導入であれば、方向性の修正も柔軟に行え、プロジェクト全体への影響を抑制可能です。
データ基盤は長期的に育てていくものであり、段階的な拡張と運用体制を前提にすることを意識して、自社に最適なシステムを構築しましょう。
データガバナンス体制を同時に構築する
データを一元管理することは、利便性と裏腹にセキュリティリスクやデータ品質の劣化リスクも伴います。「誰がどのデータにアクセスできるのか」「データの品質をどう担保するのか」といったルールを定める「データガバナンス」の体制を、データ基盤の構築と並行して整備することが極めて重要です。
活用するデータの質・量を確保する
データ基盤の導入効果を最大限に引き出すには、活用するデータの質と量を十分に確保することが不可欠です。
そのためには、信頼できるデータソースを特定し、収集対象とする情報の基準を明確にすることが重要となります。以下のような社内に存在する多種多様なデータの中から、目的に応じたデータを抽出し、定期的に更新される体制を整えます。
- 業務日報
- センサー情報
- 顧客管理データ
同時に、データの入力ルールや記録方法を標準化することで、データ品質を維持することが可能です。
また、データの量についても一定の規模が必要です。特にAIの学習には、数多くのサンプルが求められるため、データ収集の範囲や頻度を設定しておくことが望まれます。
データ分析に強いAI会社の選定・紹介を行います
今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
完全無料・最短1日でご紹介 データ分析に強いAI会社選定を依頼する
データ基盤についてよくある質問まとめ
- データ基盤とは?
データ基盤とは、企業が保有するデータを一元的に蓄積・加工・分析・活用するシステムを指します。単なる保管場所ではなく、データの流れを管理し、業務や意思決定に活用できるよう整備されたインフラです。
- データ基盤はどのような仕組み(構造)になっていますか?
データ基盤は、データを価値に変えるための一連の流れで構成されています。
- データソース: CRMや基幹システム、IoT機器など、データの発生源
- データ収集・連携: データを集めて後段の処理に送る
- 蓄積(データレイク): あらゆる形式の生データをそのまま保管する
- 加工(データウェアハウス): 分析しやすいようにデータを整理・統一して保管する
- 分析(データマート): 特定の部門や目的に特化してデータを活用する
- データ基盤を導入するメリットはありますか?
データ基盤を導入することで、情報を一元管理できるため、データの整合性が高まり、分析にかかる時間を短縮・効率化ができます。また、部門間の連携が促進され、リアルタイムな経営判断も可能です。
- クラウド型とオンプレミス型のどちらを選ぶべきですか?
クラウド型とオンプレミス型のどちらを選ぶかは、目的や要件によって異なります。
- クラウド型:初期投資が少なくスピーディーに導入でき、スケーラビリティにも優れているため、AI連携や他サービスとの統合に向いている
- オンプレミス型:自社内で運用するため、セキュリティや独自要件への対応がしやすく、ガバナンスを重視する場合に適している
将来的な拡張を考慮するなら、ハイブリッド型も有効です。
- データ基盤があると、AI導入はどう変わりますか?
データ基盤によって高品質なデータが供給されることで、AIの学習精度が高まり、モデルの精度や汎用性も向上します。また、リアルタイムでのデータ更新が可能になれば、継続的な改善や運用もスムーズに行えます。
まとめ
データ基盤は、企業がAI活用や業務の効率化を進める上で不可欠な土台です。データの蓄積・加工・分析を一つのシステムとして統合することで組織全体で情報が共有され、迅速な意思決定が実現できます。
また、自社専用のAIシステムを構築する際にも、信頼性の高いデータ基盤がAIの精度と効果を支える役割を果たします。
データ基盤の導入・構築においては、導入目的を明確にし、スモールスタートでの試行から段階的に拡張していくアプローチを検討するとよいでしょう。
実際に「自社の業務に最適なツールは何か」「将来を見据えた拡張性のある設計とはどういうものか」といった具体的な計画に落とし込むには専門的な知識や知見が不可欠です。
もし、データ基盤の構築やデータ活用戦略の策定でお困りのことがあれば、実績豊富な専門家に相談することが、成功への確実な一歩となります。

AI Market 運営、BizTech株式会社 代表取締役|2021年にサービス提供を開始したAI Marketのコンサルタントとしても、お客様に寄り添いながら、お客様の課題ヒアリングや企業のご紹介を実施しています。これまでにLLM・RAGを始め、画像認識、データ分析等、1,000件を超える様々なAI導入相談に対応。AI Marketの記事では、AIに関する情報をわかりやすくお伝えしています。
AI Market 公式𝕏:@AIMarket_jp
Youtubeチャンネル:@aimarket_channel
TikTok:@aimarket_jp
運営会社:BizTech株式会社
掲載記事に関するご意見・ご相談はこちら:ai-market-contents@biz-t.jp

