ナレッジマネジメントとは?概要・手法・メリット・生成AI(RAG)導入方法を徹底解説!
最終更新日:2025年11月17日
記事監修者:森下 佳宏|BizTech株式会社 代表取締役
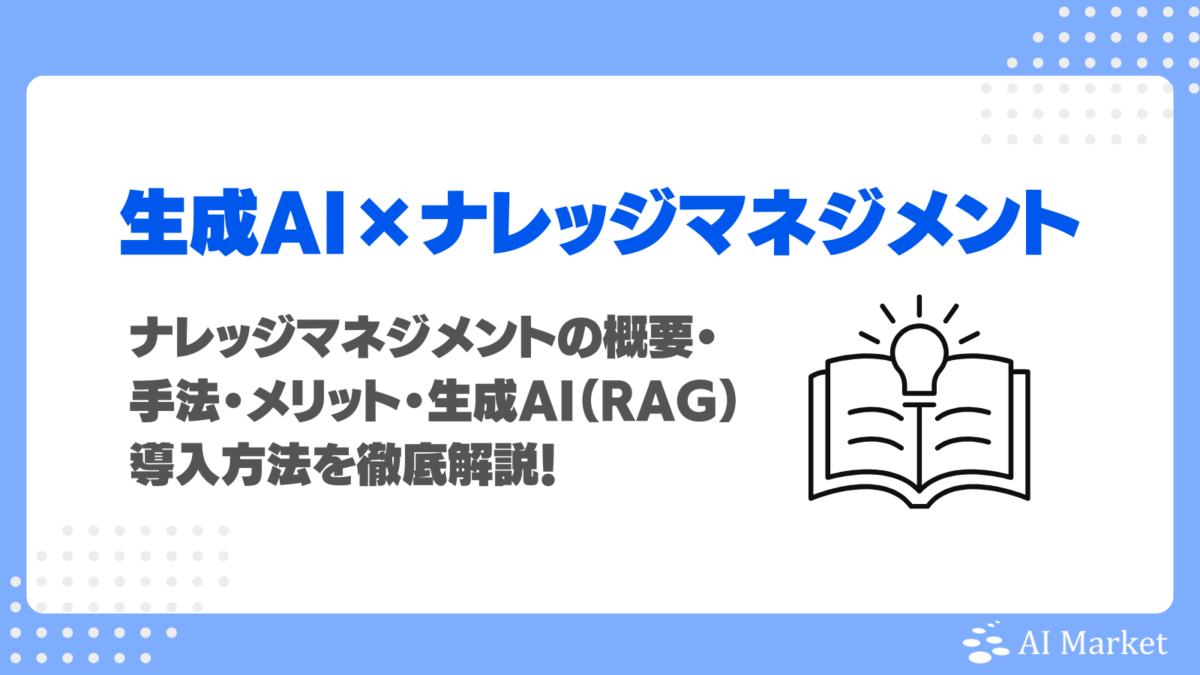
- 従来のナレッジマネジメントは、「入力の手間」「検索性の低さ」「情報の陳腐化・サイロ化」が壁
- 生成AI(特にLLMとRAG)は、文書や会話から知識を自動で抽出し、キーワードではなく「意味」で検索可能に
- AI導入の成功には、参照させる「データの品質(GIGO)」と「アクセス権限の管理」が不可欠
「ナレッジマネジメント」と聞いて、過去に導入したものの、いつしか使われなくなった社内Wikiや共有フォルダを思い出す方は少なくないでしょう。
しかし、生成AIの進化によって、大きな転換期を迎えています。特にLLM(大規模言語モデル)やRAG(検索拡張生成)などの技術は、知識の収集・整理・共有・再利用のプロセスを根本から変えつつあります。
従来のように人が手作業でナレッジを整理するのではなく、AIが文脈を理解し、最適な形で知識を活用できる時代が到来しつつあります。
この記事では、従来のナレッジマネジメントがなぜ機能しなかったのかを再確認し、AIがその「入力」「検索」「活用」の壁をどう打ち破るのかを、RAGなどの技術的な側面も交えて解説します。
LLM×RAGに強い会社の選定・紹介を行います 今年度RAG相談急増中!紹介実績1,000件超え! ・ご相談からご紹介まで完全無料 完全無料・最短1日でご紹介 LLM×RAGに強い会社選定を依頼する
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
目次
ナレッジマネジメントとは?
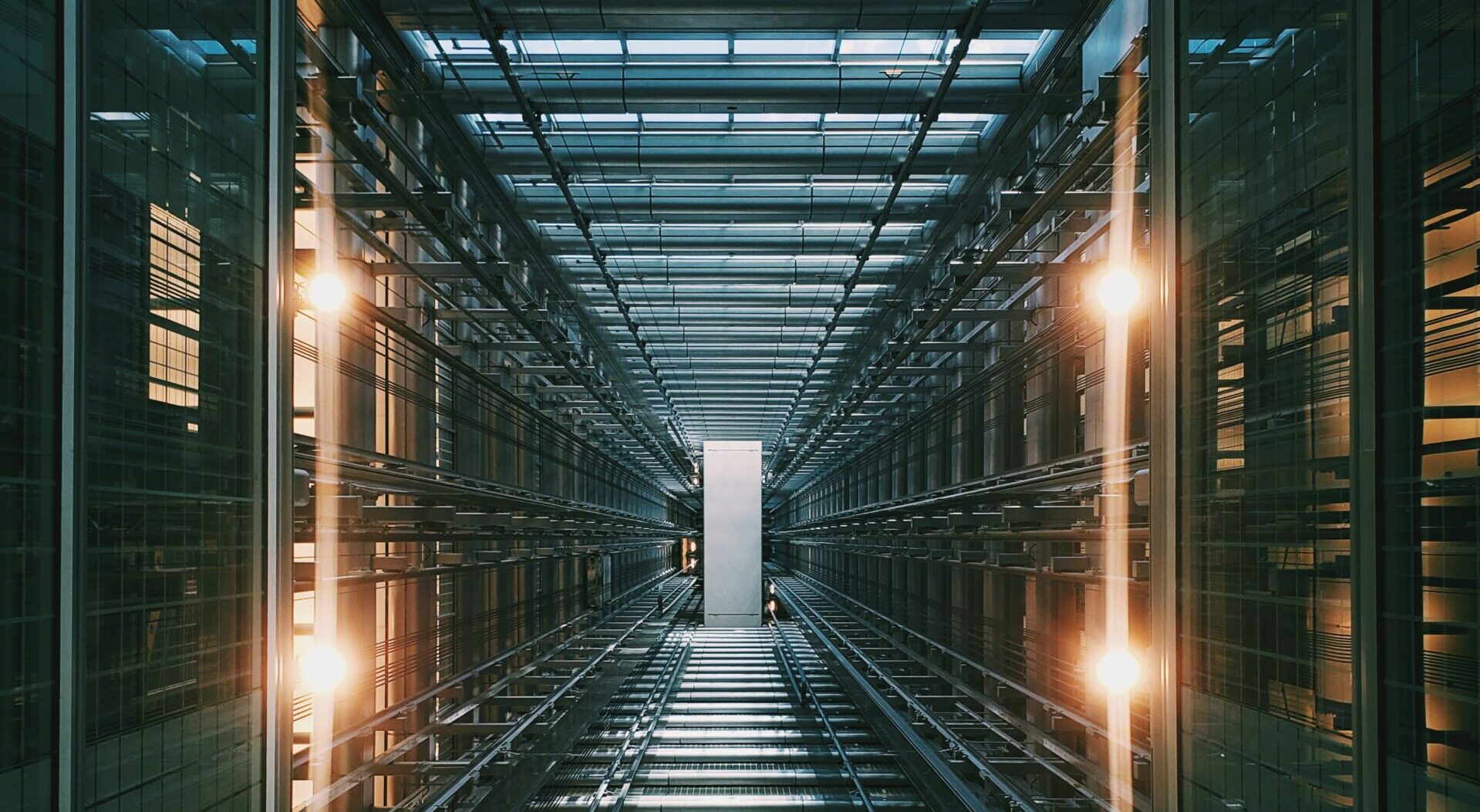
ナレッジマネジメントとは、企業内に蓄積された知識(ナレッジ)を管理し、全社的に共有・活用するための経営手法を指します。社内に貯まっている知識を資産と捉え、個人のスキルや経験、プロジェクトのノウハウなどを最適化することで、業務効率の向上やイノベーション創出につなげる効果が期待できます。
現代の企業活動では日々以下のような膨大な情報が発生します。
- 営業報告
- 顧客データ
- 設計図面
- 議事録
これらを個人の頭の中やローカルフォルダに留めておくと、知的生産性は著しく低下します。ナレッジマネジメントは、こうした情報を、誰でも・すぐに・再利用できる状態に整備し、組織の知識循環を促進することを目的としています。
特に生成AIが普及した近年では、知識の蓄積と活用のスピードが飛躍的に向上する機会といえます。社員の経験や判断基準といった暗黙知までをデジタル化し、組織全体の学習力を高めることが求められています。
ナレッジマネジメントは、企業の継続的成長を支える「知のインフラ」として、今もなお重要な経営基盤といえます。
暗黙知を形式知へ変換する
ナレッジマネジメントにおいて核心となるのは、個人の頭の中に存在する暗黙知を、誰もが理解・再利用できる形式知へと変換するプロセスです。
暗黙知とは、経験、直感、現場感覚といった言語化しづらい知識を指し、熟練者の判断やノウハウに多く含まれています。一方、形式知はマニュアル・報告書のように文章や図表で共有可能な知識を指します。
暗黙知を放置すると属人化や業務の停滞が発生します。特定の社員しか対応できない業務が増え、退職や異動があると貴重な知識が失われるリスクも高まります。
これを防ぐためには、得られた知見をデータやテキストとして記録・共有する、つまり形式知化することが不可欠です。
暗黙知を形式知に変換することは、知識を資産として循環させ、変化に強いナレッジドリブンな組織へと進化させるプロセスでもあるのです。そのため、企業はナレッジマネジメントに取り組むべきといえます。
古いナレッジマネジメントをAIが変える
一方で、ナレッジマネジメントは時代遅れと捉えられることがあります。クラウドサービスやAIツールの台頭によって、文書を共有する従来の管理方法は形骸化した印象を持たれがちです。
実際、ナレッジマネジメントによって文書化・共有されたデータの多くが情報の蓄積だけに偏り、活用や循環には至らなかったケースも多くあります。データベースが増えても検索性や再利用性が低く、現場の負担が大きくなるという問題を抱えていました。
一方、生成AI技術の進歩によってLLM(大規模言語モデル)やRAG(検索拡張生成)の登場により、ナレッジマネジメントの在り方は根本から変わりつつあります。AIが情報の意味を理解し、文脈に応じて知識を結びつけることで動的な知識活用へと進化しているのです。
つまり、古いとされるのはナレッジマネジメントそのものの仕組みではなく、実装するための手段が該当します。AIを活用していけば、ナレッジマネジメントは現代でも十分有効です。
LLM×RAGに強い会社の選定・紹介を行います 今年度RAG相談急増中!紹介実績1,000件超え! ・ご相談からご紹介まで完全無料 完全無料・最短1日でご紹介 LLM×RAGに強い会社選定を依頼する
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
代表的なナレッジマネジメント手法4選

ナレッジマネジメントには、目的や組織文化に応じてさまざまな実践方法があります。ここでは、企業で活用される4つの代表的な手法を解説します。
ベストプラクティス共有型
ベストプラクティス共有型とは、成功事例や効果がある手法を組織内で共有して全社員のスキルや生産性を底上げする手法です。営業、製造、カスタマーサポートなどの現場で実際に成果を上げた手法を再現可能な知識として蓄積・展開することで、組織全体の業務品質を均一化します。
この手法の中心となるのは、成功の再現性です。営業成績の高い社員のアプローチ方法を共有すれば、他のメンバーも同じ成果を出しやすくなります。
また、プロジェクトの成功要因や失敗の教訓を文書化・共有することで同じ課題を繰り返しにくくなります。
これまでは文書や社内ポータルを通じた共有が中心でした。近年では生成AIを活用し、チャット形式で成功事例を探すことが可能になっています。
AIが自動検索し、要点を抽出して提示することも可能です。
専門知識ネットワーク型
専門知識ネットワーク型とは、特定分野の知識やスキルを持つ専門家同士、または専門家と現場担当者をつなぐことで知識を動的に共有するナレッジマネジメント手法です。文書化された情報だけでなく、「誰が何を知っているか」という人的ネットワークそのものを活用できる点が特徴です。
専門知識ネットワーク型の目的は問題解決のスピードと質を高めることです。製造現場で発生したトラブルに対応しきれない場合に他部署の人に相談できれば、原因究明や対策立案は大幅に効率化されます。
また、社内SNSやチャットグループを通じて、社員が自発的にナレッジを共有する文化を醸成することも重要です。
さらに、AIが相談相手を自動でレコメンドすることも可能です。ナレッジネットワークの形成が属人的ではなく、システム的に促進されるようになりつつあります。
知的資本活用型
知的資本活用型とは、企業が保有する知識・ノウハウ・人材・組織文化などを「知的資本」と捉え、最大限に活用するナレッジマネジメント手法です。知識そのものを価値創出の原動力と位置づけ、戦略的に運用します。
知的資本は一般に、以下の3つの要素に分けられます。
- 人的資本(人のスキルや経験)
- 構造資本(仕組みやデータベース、プロセス)
- 関係資本(顧客やパートナーとの信頼関係)
知的資本活用型のナレッジマネジメントでは、これらを統合的に管理し、組織全体のイノベーション力や競争優位性を高めることを目指します。
例えば、熟練技術者のノウハウをAIでモデル化し、業務支援ツールに展開することで専門知識を全社展開できます。また、顧客との関係性から得たデータを分析し、製品開発やマーケティングに反映することでパーソナライズされた対応が可能です。
社内ナレッジを単なる記録ではなく、企業価値を生む資産として循環させることが知的資本活用型ナレッジマネジメントの本質です。
顧客データ共有型
顧客データ共有型は、部門ごとに分散している顧客情報を統合・共有し、全社で一貫した顧客対応を実現するナレッジマネジメント手法です。各部門が持つデータを相互に連携させることで、顧客満足度やLTV(顧客生涯価値)の最大化に直結します。
顧客データ共有型の目的は、収集した顧客データを知識として再利用することにあります。過去の問い合わせ履歴や提案内容を分析し、商品・サービスの改善に反映させることでデータが経験知として組織に循環するようになります。
近年では、AIが顧客データを横断的に参照しながら、最適な提案書や回答を自動生成するシステムも実現しつつあります。顧客データ共有型のナレッジマネジメントは、企業と顧客の関係を深化させる役割を担います。
従来のナレッジマネジメントが抱える7つの問題

多くの企業がナレッジマネジメントに取り組む中で、以下のような問題に直面することになります。重要なポイントは、以下の問題はすべて、知識を「人間」が手動で入力し、手動で検索し、手動で活用することを前提としていたために起きた必然的な失敗であることです。
貧弱な検索性
従来のナレッジマネジメントで深刻な課題の一つとされるのが、検索性の低さです。ナレッジを蓄積するためのシステムやデータベースを導入しているものの、必要な情報にすぐアクセスできないという状況に陥る企業も多いでしょう。
しかし、キーワード検索に依存する従来の仕組みでは、表現揺れや専門用語により、関連情報を網羅的に取得することが困難です。「”アレ”に関する資料…」といった曖昧な記憶では永久にたどり着けません。
特に業務現場では、同義語・略語・文脈によって使われる用語が異なるため、単純な文字一致検索では目的の情報にたどり着けないケースが多発します。そうなると、情報が存在していても見つけられない状態となり、ナレッジの再利用が進まなくなります。
情報のサイロ化
サイロ化とは、部門やチームごとに情報が閉じてしまう状態を指します。部署単位でナレッジを管理してしまうと、情報が縦割りに分断され、組織全体で知識を共有・活用することが難しくなります。
部署の違いに加えて、SharePoint、Google Drive、Slack、Teams、Confluence、個人のPCなどあらゆるプラットフォームに分散している状態も多いのではないでしょうか。
サイロ化が進行すると、同じ課題に対する調査・検証が重複するなど非効率な業務が発生するようになります。また、顧客対応や製品開発のように複数部門の連携が必須となる領域で、情報共有の遅れが機会損失につながるケースもあります。
さらに問題なのは、部門ごとの文化やシステムが異なることで知識の流通経路が断絶してしまうことです。以下のように利用するプラットフォームが異なれば、情報を相互に参照することが困難になります。
- 営業部:CRM
- 開発部:社内Wiki
- カスタマーサポート:FAQツール
結果として、知識が特定の部門に固定化され、全社的な学習やイノベーションの妨げとなってしまうのです。
煩雑な入力UI/UX
従来型のナレッジマネジメントでは、情報登録の入力や操作性が障壁となってきました。記載項目が多すぎる、分類タグの選択が煩雑といった問題を抱えるケースはよく見られます。
また、以下のような状況が常態化すると現場や営業職などモバイル中心のユーザーが利用しづらく、知識共有の偏りを生む要因にもなります。
- 入力画面が直感的でない
- PC操作が前提となる
- 入力UIが統一されていない
結果としてナレッジの蓄積が進まず、システムが形だけの存在になるという悪循環に陥るのです。
情報の陳腐化
ナレッジマネジメントにおける大きな問題の一つが、蓄積された情報の陳腐化です。登録されたナレッジが更新されないまま放置されると内容が古くなり、誤った判断を招くリスクが高まります。
特に、業界動向・製品仕様・法令などが頻繁に変化する分野では情報の鮮度が業務品質に直結します。更新頻度が低い状態では、現場の知見や新しい成功事例が反映されず、ナレッジベースが過去の記録庫にとどまってしまいます。
以下のような状況ではナレッジが死蔵データと化し、古い情報が混在するようになります。
- 情報登録後のメンテナンスが属人的になっている
- 誰が・いつ・どの情報を更新するのかが定義されていない
結果として、利用するたびに都度確認しなければならず、システム全体への信頼性は低下していくでしょう。使えないシステムをあきらめ、結局は「〇〇さんに聞く」という最も原始的な手段に戻っていきます。
そして、そのベテラン社員の退職や転職が、組織にとっての致命的な「知識の損失」となるリスクを抱え続けます。
完璧主義による分類体系の破綻
従来のナレッジマネジメントでは、情報を正しく整理することに重きを置きすぎる状況がよく観察されました。結果として、分類体系が複雑化し、運用が破綻するケースが多く見られています。
理想的なカテゴリ構造を作ろうとするあまり、利用者がどこに登録すべきか、どこを探せばよいか分からなくなるのです。
特に大企業や多事業部制の組織では、業種別・製品別・部門別・テーマ別など複数の分類軸が混在します。その結果、同じ情報が複数箇所に登録されたり、逆にどのカテゴリにも属さない知識が発生したりとナレッジベースの整合性が失われてしまいます。
また、誤った分類を避けたいという意識からナレッジの登録を先送りにする傾向も生まれやすくなります。完璧を目指すあまり、ナレッジ共有のスピードと柔軟性が犠牲になるのです。
こうした完璧主義的な設計思想は、知識を動的に活用するというナレッジマネジメント本来の目的と矛盾します。結局は「使われない」ナレッジマネジメントシステムへと変貌してしまいます。
知識共有のインセンティブ欠如
従来のナレッジマネジメントが形骸化する要因として、社員が知識を共有する動機を持てないこと、つまりインセンティブの欠如が挙げられます。
ナレッジ共有を任意としている企業は少なくありません。しかし、それでは評価や報酬に結びつかないため、日常業務の優先順位として後回しにされがちです。
一方の現場社員にとって、ナレッジ登録は時間と労力を要する作業と捉えられているかもしれません。そもそも、「トラブルシューティングの勘」や「顧客のニュアンスを汲み取った提案」といった高度な暗黙知はテキスト化すること自体が困難です。
さらに、忙しい現場のエースやベテランほど、自らのノウハウを文書化する時間を持ちません。「自分のナレッジをまとめるより、目の前の業務を片付けたい」のが本音です。
にも関わらず、共有しても自分の成果が見えづらく、誰が活用しているのかも分からない環境では、継続的な蓄積は期待できません。
さらに、共有した内容が批判や指摘の対象になる文化があれば、リスクを取ってまで発信しない方がよいという心理が働き、ナレッジ循環は停滞します。
間違った目標(KPI)設定
管理側が共有数や閲覧数といった定量的なKPIだけを重視すると、質の高いナレッジが蓄積されず、形だけの運用に陥ることもあります。知識共有が評価制度・人材育成・組織文化の中でどのように位置づけられるかが明確でなければ、社員は自分ごととして捉えにくいのです。
LLM×RAGに強い会社の選定・紹介を行います 今年度RAG相談急増中!紹介実績1,000件超え! ・ご相談からご紹介まで完全無料 完全無料・最短1日でご紹介 LLM×RAGに強い会社選定を依頼する
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
ナレッジマネジメントに生成AIを導入してできるようになること

生成AIの核心技術であるLLM(大規模言語モデル)とRAG(検索拡張生成)を導入することで、ナレッジマネジメントは課題を解決し、知識を活用できるようになります。
関連記事:「RAGで属人化解消を実現?生成AIのナレッジマネジメント導入メリットや部門別活用シーンを徹底解説!」
キーワードの一致から意味を理解した検索が可能になる
LLMとRAGを組み合わせることで、AIは文脈や意味を理解・一致させることに基づいて情報を抽出できるようになります。
「営業資料の作成方法」と検索した際に、「提案書 テンプレート」や「顧客向けプレゼン資料」など、直接的なキーワードが含まれない関連ドキュメントも自動的に提示されます。
また、RAGによってナレッジベース全体を横断的に検索し、複数の情報源を統合して最適な回答を生成します。結果として、ユーザーが曖昧な質問をしても、文脈に即した正確な情報を迅速に取得できるようになります。
それによってデータを探す手間が減り、知識が自然に見つかる環境を実現できるようになって従来の貧弱な検索性を根本から解消します。
ベクトルデータベースによって横断検索でサイロ化を解消
部門間で情報が分断されるサイロ化については、ベクトルデータベースの導入によって改善可能です。
ベクトルデータベースは、テキスト、画像、音声を数値ベクトルとして保存し、意味的な類似度に基づいてセマンティック検索(意味検索)を行う技術です。異なるシステムやフォーマットに存在する情報を横断的に検索し、部門の壁を越えた知識連携が可能になります。
これにより、ナレッジへのアクセスがシームレスになり、検索作業は大幅に効率化できます。例えば、「過去3年のA社向けの提案で、競合と比較した時の自社のストロングポイントをまとめた資料」と曖昧に入力しても、AIは文脈を理解し、該当する資料(や、資料の該当箇所)を提示します。
また、LLMはRAGによる検索結果を統合・要約し、複数ソースの知見をまとめた回答を生成します。結果として情報の孤立が解消され、組織全体で知識が循環する状態を実現することが可能です。
チャットUIだけで入力が完結する
複雑な入力フォームや煩雑な操作の課題については、LLMを活用したチャットUIの導入によりナレッジ登録のハードルが劇的に下がります。ユーザーは自然言語で対話するだけで自動的に要点が整理され、カテゴリ分けやタグ付けまで行ってくれます。
「今日の顧客対応で得られた学びを記録したい」とチャットで入力すると、AIが内容を解析し、タイトル・要約・キーワードを自動生成します。ユーザーは入力形式や分類ルールを意識する必要がなく、会話ベースで直感的にナレッジを登録できます。
非構造データのデータ化
Slackでのやり取り、メール、提案書(Word, PDF)、設計図など、これまで「検索不可能」とされていたフォーマットのデータ(非構造化データ)から文脈を読み取り、知識として蓄積できます。
さらに、ZoomやTeamsでの会議音声は、AIが自動で文字起こしし、要点を「サマリー」と「ToDoリスト」にまで整理してくれます。PC操作を前提とした従来型システムと異なり、モバイルや現場端末からも即座に投稿できるため即時性も高くなります。
関連記事:「RAGのデータ収集を成功させる方法は?目的別の考え方・コツ・ツール・外部データ収集手段を徹底解説!」
自動更新・再学習で最新知識が参照される
情報の陳腐化についても、LLMとRAGを組み合わせたナレッジ基盤を構築することで、AIが最新情報を学習・更新し続けられるようになり、自動的にアップデートされる仕組みとなります。
AIは新たに追加されたドキュメントやチャット履歴などを解析し、既存のナレッジと照合して内容の古さ・重複を検出します。例えば、法改正や製品仕様の変更が発生した場合、関連ナレッジを自動で特定します。
これによって人手による定期メンテナンスに頼らず、常に信頼性の高い状態を維持できます。
さらに、RAGによる検索では、ユーザーが参照するタイミングで最新データをリアルタイムに呼び出し、生成AIが新しい情報を反映した回答を提示します。情報そのものを更新しなくても、常に最新の知識を引き出せる状態が実現するのです。
AIが文脈から最適カテゴリを提案
完璧主義的な分類体系の破綻に対し、LLMは最適カテゴリを提案し、ナレッジが使われない状態を防ぎます。AIが入力テキストの文脈や目的を理解し、カテゴリやタグを自動的に提案することで悩むことなく知識を整理できるようになります。
「新製品の導入時に発生したトラブルの対応手順」と入力すると、AIがその文脈から製品導入・トラブルシューティングといった分類を推定し、自動でタグ付けを行います。必要に応じて複数のカテゴリへ登録することも提案されるため、情報の重複や登録ミスを防ぎます。
さらに、AIはナレッジの利用傾向を学習し、カテゴリ構造そのものを自動で最適化することができます。利用頻度が低い分類を統合したり、新しいテーマに対応するカテゴリを生成したりと自然に体系が進化していきます。
このように、AIによって文脈理解と分類提案を取り入れることで、AIが継続的に調整する柔軟な知識構造へ転換が可能になります。
回答の見える化と貢献度トラッキングでモチベーション向上
LLMやRAGを活用した次世代型ナレッジマネジメントでは、AIが知識の利用状況を自動的にトラッキングし、貢献度を見える化するシステムが構築できます。
共有されたナレッジがどの程度閲覧され、どの課題の解決に貢献したのかをAIが解析し、数値化して可視化します。「この回答が5件の問い合わせ解決に活用されました」「この文書が営業部で最も参照されています」といったフィードバックを自動表示することで、ユーザーが共有したナレッジの貢献度を数値化可能です。
貢献度データを人事評価やスキルマップと連携させることで、知識共有を評価対象として位置づけることも可能です。これにより、「共有するほど自分の価値が上がる」というポジティブな動機を浸透・定着できます。
回答の可視化と貢献度トラッキングによって、知識共有は「会社に認められる行為」へと変化し、組織全体の学習意欲とエンゲージメントを高める原動力となるでしょう。
答えの根拠(Citation)を提示
RAGによるナレッジマネジメントが従来のシステムと決定的に違うのは、根拠(Citation)を明示できる点です。
RAGを使えば、AIの回答がWeb上の一般的な情報なのか、それとも社内情報なのかが一目でわかります。例えば、クライアントのシステムで生じた障害の復旧方法について、ウェブ上で公開されている使用機器メーカーの取扱説明書の情報と、社内で蓄積されてきたクライアントの障害報告書を分別できる仕方で回答してくれます。
RAGによって、ハルシネーション(うそ)のない情報を引用根拠付きで回答できるようになりました。
ナレッジマネジメントについてよくある質問まとめ
- ナレッジマネジメントとは何ですか?
ナレッジマネジメントとは、企業内に蓄積された知識やノウハウを収集・整理し、全社で共有・活用するための仕組みを指します。暗黙知を文書やデータとして形式知化し、組織全体で再利用することで、生産性向上やイノベーション創出を目指します。
- ナレッジマネジメントはもう古いのですか?
ナレッジマネジメントは古いどころか、AI時代において再び注目されています。従来のナレッジマネジメントは情報を貯める仕組みに偏っていましたが、現在ではAI技術によって知識を自動で整理・更新・再利用できる動的なナレッジマネジメントへと進化しています。
- 従来のナレッジマネジメントは、なぜ失敗しやすいのですか?
主に以下の7つの問題が原因です。
- 貧弱な検索性: キーワードが完全に一致しないと必要な情報が見つかりません。
- 情報のサイロ化: 部署やツールごとに情報が分断され、横断的に探せません。
- 煩雑な入力UI/UX: 情報の登録が面倒で、現場の負担が大きく継続されません。
- 情報の陳腐化: 更新が止まり、古い情報が放置されることでシステム全体の信頼性が失われます。
- 完璧主義による分類の破綻: 分類ルールを複雑にしすぎ、利用者が登録・検索できなくなります。
- インセンティブ欠如: 知識を共有することへの動機付け(評価など)が弱く、後回しにされます。
- 間違った目標(KPI)設定: 登録件数など、質より量を見るKPIが設定されがちです。
- ナレッジマネジメントにLLMやRAGを導入するメリットは?
従来の課題をAIが以下のように解決します。
- 検索性の向上: キーワード一致ではなく、文脈や「意味」を理解して検索(セマンティック検索)できます。
- サイロ化の解消: ベクトルデータベース技術により、異なるシステム間の情報を横断検索できます。
- 入力の簡易化: 会議音声の自動要約や、チャット入力だけでAIが内容を整理・登録を支援します。
- 非構造化データの活用: Slackの会話やPDF、音声データなど、これまで検索対象外だった情報も知識として扱えます。
- 陳腐化の防止: AIが最新情報を自動で学習・参照(RAG)し、常に新しい情報に基づいた回答を生成します。
- 分類の自動化: AIが文脈を理解し、最適なカテゴリやタグを自動提案するため、整理の手間が省けます。
- 貢献度の可視化: 誰の知識がどう役立ったかをAIがトラッキングし、共有のモチベーション向上に繋げられます。
- 根拠の提示: AIが回答の根拠となった社内文書(Citation)を明示するため、信頼性が向上します。
まとめ
ナレッジマネジメントは、企業が蓄積したままにしていた知識を再構築し、価値を創出するための経営戦略です。そして、いま求められているのは、AIが自律的に学習し続ける動的なナレッジマネジメントシステムへの転換です。
LLMやRAGの登場によって、知識の発見・整理・更新・評価のすべてのプロセスをAIが支援できるようになりました。ナレッジマネジメントが抱えていた課題は、もはや個別の課題ではなく、AIが一体的に解決できる領域となっています。
しかし、そのポテンシャルを最大限に引き出すには、自社のデータがどこに、どのような品質で存在しているかの棚卸しや複雑なアクセス権限の管理といった導入企業固有の課題解決が不可欠です。
「どのSaaSを選ぶべきか」「自社の機密データをどう安全にRAGで活用するか」「既存システムとどう連携させるか」といった具体的な設計・実装には、深い技術的知見と豊富な導入経験が求められます。
AIを活用した真のナレッジマネジメントを実現し、組織の競争力を高めるための一歩として、まずは専門家にご相談ください。

AI Market 運営、BizTech株式会社 代表取締役|2021年にサービス提供を開始したAI Marketのコンサルタントとしても、お客様に寄り添いながら、お客様の課題ヒアリングや企業のご紹介を実施しています。これまでにLLM・RAGを始め、画像認識、データ分析等、1,000件を超える様々なAI導入相談に対応。AI Marketの記事では、AIに関する情報をわかりやすくお伝えしています。
AI Market 公式𝕏:@AIMarket_jp
Youtubeチャンネル:@aimarket_channel
TikTok:@aimarket_jp
運営会社:BizTech株式会社
掲載記事に関するご意見・ご相談はこちら:ai-market-contents@biz-t.jp

WEBから無料相談(60秒で完了)
今年度問い合わせ急増中
Warning: foreach() argument must be of type array|object, false given in /home/aimarket/ai-market.jp/public_html/wp-content/themes/aimarket/functions.php on line 1594
Warning: foreach() argument must be of type array|object, false given in /home/aimarket/ai-market.jp/public_html/wp-content/themes/aimarket/functions.php on line 1594
