RAGで属人化解消を実現?生成AIのナレッジマネジメント導入メリットや部門別活用シーンを徹底解説!
最終更新日:2025年10月28日
記事監修者:森下 佳宏|BizTech株式会社 代表取締役

- RAGとLLM(生成AI)で社内に散在するマニュアルや報告書などの文書をAIが検索し、その内容を根拠として対話形式で分かりやすい回答を生成
- 特定の担当者しか知らなかった知識やノウハウ(暗黙知)を、誰もがアクセスできる組織の知識へと変え、業務品質の標準化
- 情報アクセスのあり方を「探す」から「尋ねる」へ変革し、意思決定の迅速化やコスト削減、組織の学習能力向上
社内に情報が散在し、特定の個人の経験に依存する「業務の属人化」は、多くの企業が抱える生産性低下やリスクの温床です。
本記事では、この根深い課題を解決する手段として注目される、RAG(検索拡張生成)とLLMを組み合わせた生成AI型の新しいナレッジマネジメント手法の仕組みとメリット、そして活用シーンを解説します。
AIが社内の膨大な文書から必要な情報を瞬時に探し出し、対話形式で回答を生成する仕組みによって、情報アクセスのあり方を根本から変えます。
LLM×RAGに強い会社の選定・紹介を行います
今年度RAG相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
完全無料・最短1日でご紹介 LLM×RAGに強い会社選定を依頼する
目次
RAGでどうやって業務の属人化を解消する?
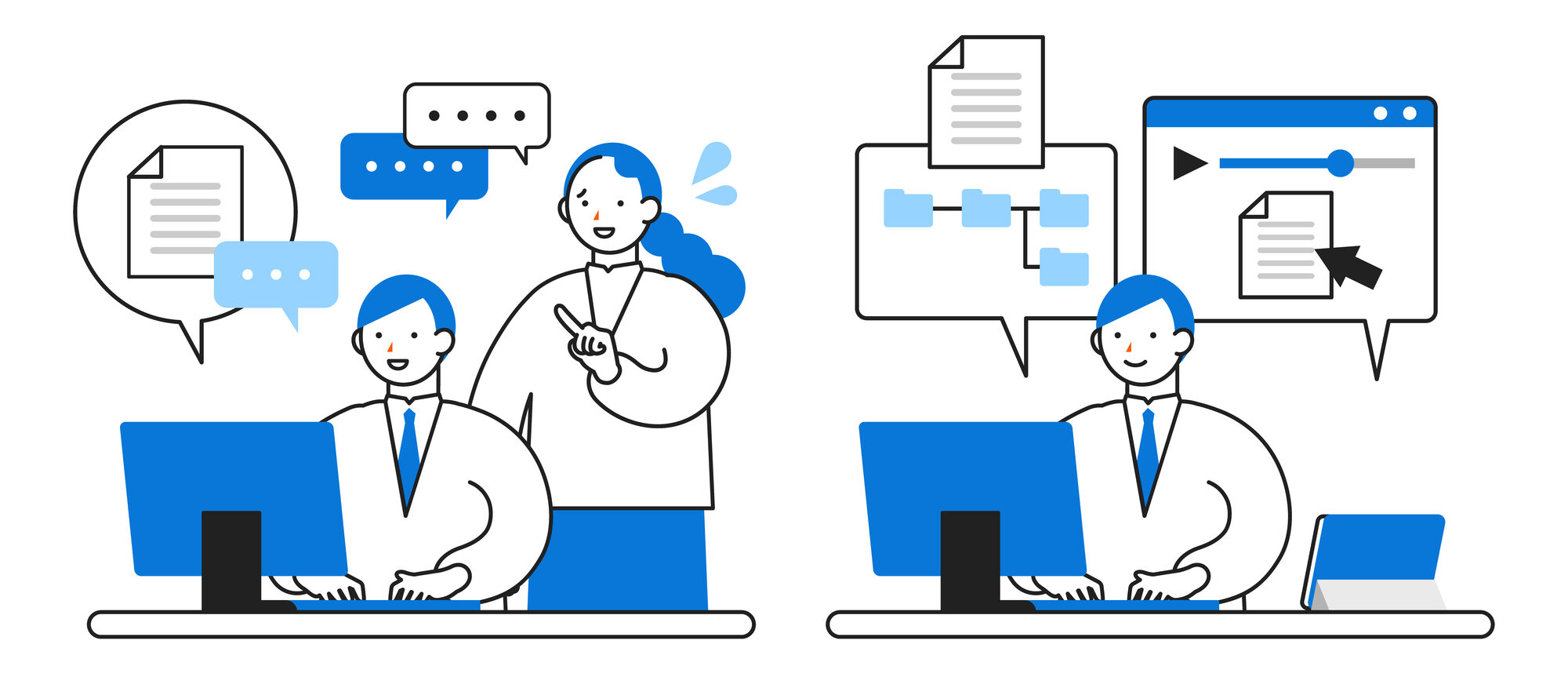
業務の属人化は、特定の担当者に知識やノウハウが集中することで、組織全体のパフォーマンスやリスク管理に悪影響を及ぼします。この課題に対し、ChatGPTのようなLLM(大規模現モデル)とRAG(拡張検索生成)を組み合わせることで、戦略的な解決策を提案することが可能です。
従来のLLMは、インターネット上の膨大な情報をもとに学習していますが、社内の個別具体的なルールや過去の経緯までは把握していません。そのため、「A社との過去の取引での注意点は?」といった社内情報に関する質問には、不正確な回答(ハルシネーション)をしてしまうことがありました。
RAGは、社内ドキュメントやFAQ、業務マニュアルなどの非構造化情報を検索し、その文脈を理解します。その上で、LLMが自然な回答を生成します。
この仕組みにより、特定の担当者に依存せず、必要な知識を誰でも・即座に引き出せる環境が整います。あたかも社内のベテラン社員のように、正確な根拠に基づいた回答を迅速に提供できるのです。
さらに、RAGは検索結果の根拠を提示できるため、情報の正確性や信頼性が担保され、属人化に代わる「組織知」の活用が可能です。こうした仕組みは、判断の一貫性を保ちつつ、業務の標準化と継続的な改善を促進します。
LLMとRAGの導入による知の循環プロセス
LLMとRAGの組み合わせは、組織内の「知識の循環」を生み出す仕組みとして機能します。このプロセスは以下の4つの段階に分けられます。
- 知識の集約(インプット)
- 関連情報の抽出(検索)
- LLMによる文脈化・回答生成(活用)
- 活用後のナレッジ再蓄積(フィードバック)
インプットの段階では、社内マニュアルやFAQ、議事録、報告書など多様な形式のナレッジを収集して、データベースに蓄積します。次にRAGが質問に関連する高精度な文書情報を選定します。
そしてLLMによる文脈化・回答生成を通じて、検索結果をもとに、自然で分かりやすい回答を生成することで、実務に即した回答を得られます。
さらに重要なのが、活用後のナレッジ再蓄積(フィードバック)です。ユーザーの質問履歴や回答活用の実績をもとに新たなナレッジとして蓄積・学習していくことで、システムは継続的に進化し、知の鮮度と精度が高まります。
このような知識の流動性は、従来の属人的な暗黙知に依存しない学習体制を生み出し、企業の競争力強化につながります。
関連記事:「LLMとRAGで社内情報検索を効率化!検索・活用における役割」
LLM×RAGに強い会社の選定・紹介を行います
今年度RAG相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
完全無料・最短1日でご紹介 LLM×RAGに強い会社選定を依頼する
LLMxRAGを用いた生成AI型ナレッジマネジメントを導入するメリット

LLMとRAGによるナレッジマネジメントは、業務の属人化を防ぎながら、組織全体の知識活用を促進します。具体的なメリットは以下です。
属人化を解消した業務の安定性確保
業務の属人化は、担当者の退職や異動に伴い、リスクが高まります。特定の人物にしかわからない情報や手順がある状態では、業務の継続性や品質が損なわれ、組織全体のパフォーマンスにも悪影響を及ぼします。
そこでRAGは、社内の文書や業務フローなどを横断的に検索し、信頼性のある情報源をもとに回答を提示します。これにより、これまで担当者の頭の中にあった暗黙知としてのノウハウが、誰でもアクセス可能なナレッジへと変換されます。
さらに、LLMが質問の文脈を理解し、業務上の意図に合った自然な回答を提示することで、出力内容に手を加えず活用できるという現場への即応力も高まります。
属人化を解消することで、誰が担当しても一定の品質で業務を遂行できる体制が整い、組織は安定的・持続的な運営が可能となります。近年では人材の流動性が高まっているため、こうした業務の安定性は企業経営における重要な基盤といえるでしょう。
「探す」から「尋ねて対話」による情報アクセス
従来のナレッジマネジメントは、ユーザーが適切なキーワードを考えて検索するのが基本でした。しかし、LLM×RAG環境では、AIに対して以下のように人間と話すように自然な言葉で質問するだけです。
- 従来: [営業日報] [A社] [トラブル] [解決策]
- LLM×RAG: 「昨年、A社のプロジェクトで発生したトラブルについて、最終的な解決策と顧客の反応を要約して教えて。」
AIが文脈を理解し、複数の資料を横断して情報を整理・要約した上で回答を生成するため、ユーザーは資料を探し回る時間から解放されます。
さらに、このLLM×RAGの仕組みを「ツールの一つ」として使いこなし、より高度なタスクを実行するアーキテクチャが「Agentic RAG」です。
LLM×RAGが「情報アクセスの効率化(尋ねて対話)」であるのに対し、Agentic RAGは「業務プロセスの自動化(尋ねて実行)」を実現します。
Agentic RAG環境下のAIエージェントは、単に情報を要約して提示するだけでなく、その情報に基づいて「次に何をすべきか」を自ら計画し、外部ツール(CRM、チャットツール、データベースなど)と連携して実行まで行います。
情報のサイロ化から知識の統合へ
多くの場合、社内の情報はSharePoint、Teams、Salesforce、独自データベースなど、様々な場所に散在しています。RAGはこれらのバラバラな情報源を連携させるハブとして機能します。
例えば、「最新の製品Xに関する技術資料と、それを使った営業の成功事例を教えて」と尋ねるだけで、AIは開発部門のドキュメントサーバーと営業部門のCRMから関連情報を抽出し、統合された一つの回答を生成します。
これにより、部門の壁を越えた知識の連携が生まれ、新たなイノベーションの土壌となります。
死蔵ナレッジを「生きたナレッジ」として共有・活用
これまでの社内Wikiやファイルサーバーは、情報を保管するだけの「倉庫」でした。結果として以下のような構造化されていないナレッジの多くは、一度作成されたまま活用されず、「死蔵ナレッジ」として埋もれているのが実情です。
- 業務に活用した資料
- 会議の議事録
- 報告書
- マニュアル
LLMとRAGを活用することで、こうしたナレッジを「生きた知識」として再活用する仕組みを構築できます。
RAGは非構造化の膨大な文書データから質問に関連する情報を的確に抽出します。これにより、過去の文書も自然な言語で引き出せるようになり、知りたい情報に簡単にアクセスできる環境が整います。
結果として、過去の事例やノウハウが再評価され、業務改善や意思決定に生かされる機会を増やすことが可能です。過去の複数のプロジェクト報告書から成功の共通要因を分析させたり、顧客からの問い合わせ履歴を基にFAQの草案を作成させたりと、単なる情報検索に留まらない活用ができるようになります。
こうした仕組みは、知識の利活用によって組織の価値を高める効果もあり、経営戦略に寄与します。
意思決定の迅速化
ビジネス環境が目まぐるしく変化する現代において、意思決定のスピードは競争力を左右する要素です。しかし実際の現場では、必要な情報を探すのに時間がかかり、判断が遅れるケースも少なくありません。
こうした課題に対して、LLMとRAGを組み合わせたナレッジマネジメントは、出力情報の信頼性や文脈の正確性を担保します。これにより、従来であれば複数部門に確認が必要だった情報も一問一答で即座に取得可能となり、意思決定に必要な材料を瞬時に揃えることが可能です。
また、出典を明示できる点もRAGの強みで、根拠ある判断が行いやすくなり、意思決定の透明性も担保されます。スピードと正確性を兼ね備えた判断環境を整えることで組織全体の意思決定能力が高まり、経営判断にポジティブな影響を与えるでしょう。
問い合わせ対応や社内教育にかかるコストの削減
社内の問い合わせ対応や新人教育にかかる人的コストは、見えにくいながらも企業全体の生産性に大きく影響します。同じ質問への繰り返し対応や、OJTにおける属人的な指導は担当者の負担を増やし、本来注力すべき業務の妨げにもなりかねません。
そこで、RAGによる社内ナレッジベースをもとにした関連情報の提示とLLMによる自然な回答の出力によって、非専門部署でも理解しやすい情報提供が可能になります。これにより、ヘルプデスクや管理部門に集中していた問い合わせが自動化され、対応工数の大幅な削減が実現できます。
新人や中途社員の教育においても、基礎的な業務知識をAIが24時間対応でサポートするため、教育担当者の負担が軽減されると同時に、学習の属人性も解消されます。学習の属人化は、習得するべき知識や技術を身に付ける機会が失われ、学習内容に差が生まれる環境を生み出しかねません。
結果として、教育コストの最適化と業務のスピードアップが同時に進み、組織全体の生産性を底上げすることが可能です。企業活動において問い合わせ対応と社内教育は欠かせないだけに、コスト削減は大きなメリットとなります。
組織学習の継続的な促進
企業が持続的に成長するためには、従業員個人だけでなく、組織全体が学び続ける体制が不可欠です。LLMとRAGを活用したナレッジマネジメントは、成長に欠かせない組織学習を仕組みとして支える強力な基盤となります。
従来の知識共有は、研修資料やナレッジ共有会など限られた場に依存しており、学びが一過性になりがちでした。対してRAGは、質問が入力されればリアルタイムで関連情報を提示し、LLMが文脈に合った回答を返すことで業務そのものが学習の機会へと変わります。
これにより、日常業務を通じて知識が蓄積・活用されるという循環が生まれます。
さらに、ユーザーの検索履歴や質問傾向を分析すれば、どのような情報が不足しているかを把握できるため、ナレッジベースの改善にも有効です。このように社内ナレッジは更新され続け、組織は常に進化できる学習サイクルを確立できます。
LLMとRAGで属人化解消を実現できるユースケース

LLMとRAGの活用は、業種や部門を問わず多様な業務に応用できます。
ヘルプデスク・総務・人事:社内問い合わせ対応の自動化
ヘルプデスク、総務、人事部門では、以下のような定型的な問い合わせが日常的に発生します。
- パスワードはどうやって再発行すればいいですか?
- 社用PCに不具合が起きました
- オフィスの備品や消耗品の発注方法
- 出張申請・経費精算のフローが知りたい
- 勤怠管理・打刻修正はどうやる?
- 有給休暇の取得ルール・残日数を確認したい
こうした問い合わせ対応には時間と工数がかかり、業務の非効率化を招く要因となっていました。
そこで注目されているのが、LLMとRAGを活用した問い合わせ対応の自動化です。RAGが関連情報の即時検索を担うことで、ユーザーはチャット形式で質問するだけで社内ルールに即した必要な情報を得られるため、従来のように担当者の手を煩わす必要がなくなります。
また、対応の品質やスピードも均一化され、担当者の負担は大きく軽減されます。さらに、問い合わせ内容は蓄積・分析することによって、業務改善のヒントやFAQの精度向上にもつながります。
このような問い合わせ対応の自動化は、バックオフィス部門の生産性向上と全社的なナレッジの流通を両立させる上で重要です。
製造・IT:マニュアルや技術文書の検索サポート
製造業の現場やIT部門では、日々の業務においてマニュアル、技術仕様書、設計図など膨大なドキュメントを参照する必要があります。しかし、それらの情報は散在し、形式もバラバラであるため、必要な情報にたどり着くまでに時間を要する課題が発生しがちです。
RAGを活用すれば、このような情報探索の負担を大幅に軽減できます。RAGは構造化・非構造化を問わず、技術文書やナレッジベースから質問に関連する情報を高速で抽出します。
その上でLLMが検索結果を読み解き、従業員が理解しやすい文脈で要約・説明します。
現場担当者でも即座に必要な知識にアクセスできるようになることで、装置の設定や開発作業などの場面で判断ミスや手戻りを防ぐことが可能です。こうしたメリットは、作業効率と品質の向上にもつながります。
複雑な仕様変更や障害対応の場面では、過去の対応履歴や技術情報の再利用がカギとなるケースもあるため、蓄積されたデータを参照できるシステムは不可欠といえます。LLMとRAGによって、組織の技術知識を共有資産として活かすことが可能となり、属人化した専門知の可視化にも貢献します。
営業:過去事例検索と提案支援
営業部門の現場では、顧客の業種や課題に応じて最適な提案を行うために過去の提案事例や成功ケースを素早く把握することが求められます。しかし、案件情報や提案書は部門ごとに管理されていたり、エース営業の経験則に頼っていることも多く、必要な情報を見つけ出すには時間と労力がかかります。
こうした課題に対し、LLMとRAGは営業活動の高度化に貢献します。例えば、「製造業向けのDX提案事例はあるか」「同業他社に対してどのようなアプローチを取ったか」といった具体的な質問にも、文脈を踏まえた精度の高い回答が得られます。
これにより、提案内容の精度が高まり、顧客への対応スピードが向上します。
さらに、エースのノウハウを若手従業員にも共有できるようになるため、営業活動全体の生産性底上げにもつながります。属人化しがちな営業ノウハウを組織の資産として活用できることは、競争優位の確立にも直結するといえるでしょう。
新人教育:ナレッジ共有によるOJT負担の軽減
新人教育は企業にとって重要な投資ですが、現場任せのOJTに依存している場合、教育の質が担当者の経験やスキルに左右されがちです。加えて、基本的な質問対応や業務手順の説明に多くの時間が割かれるとなると、担当者の負担は無視できないものとなるでしょう。
こうした属人化と非効率を解消する手段として、RAGを活用したナレッジ共有の仕組みが注目されています。新人はわからないことがあればAIに質問するだけで的確な情報を得られるため、自律的な学習が促進されます。
これにより、担当者による反復的な説明作業が不要となり、本来注力すべき指導や実務支援に時間を割くことが可能です。
また、RAGが提示する情報は常に一貫性があり、アップデートの可能なため、教育内容の標準化にもつながります。結果として、新人の立ち上がりが早まり、教育コストの削減と即戦力化の両立が実現できます。
法律・契約:法務・コンプライアンスにおける情報確認
社内の法務やコンプライアンス業務では、正確性・網羅性・更新性の高い以下のような情報が求められます。
- 過去の契約書(売買契約、業務委託契約、NDA 等)
- 契約テンプレートおよび条文の解釈ガイドライン
- 自社の取引条件(支払条件、検収基準、納期 等)
- 契約更新・解約・再交渉の履歴
- 社内規程・規則(就業規則、情報セキュリティ規程、ハラスメント防止規程 等)
- 各種法改正に関する対応方針
- 取引先の反社チェック・与信管理の履歴
- 商標・特許・著作権の登録・申請情報
しかし、情報の所在が分散していたり、担当者しか理解できない解釈が存在する場合、属人化が進行しやすく、ミスや見落としのリスクが高まります。こうした課題に対し、LLMとRAGは関連資料の抽出と要点の整理・説明を担い、情報確認の信頼性と効率を大きく向上させます。
「下請法に該当する取引かどうか」「秘密保持契約の見直しが必要か」など、実務的な質問にも文脈に即した回答が得られるため、確認作業の迅速化と正確性が両立可能です。
さらに、出典情報も明示されるため、生成結果の裏付けが取りやすく、法務リスクの低減にもつながります。属人的な判断に頼らず、組織として一貫したコンプライアンス体制を築く上でも有効です。
LLM×RAGに強い会社の選定・紹介を行います
今年度RAG相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
完全無料・最短1日でご紹介 LLM×RAGに強い会社選定を依頼する
RAGでの属人化解消についてよくある質問まとめ
- RAGは属人化の解消にどのように役立ちますか?
RAGを導入することで、業務知識が特定の担当者に依存することなく、誰でも均一な情報にアクセスできるようになります。具体的には、以下のような効果が期待できます。
- 暗黙知や個人ノウハウが可視化され、再利用可能になる
- 経験年数に関係なく業務の再現性が向上する
- 属人化による情報格差や対応ミスのリスクを軽減できる
- どのような業務でRAGを使うと属人化の解消につながりますか?
RAGは以下のように、ナレッジや手順の共有が重要な業務領域で特に効果を発揮します。
- ヘルプデスク・総務・人事:よくある社内問い合わせの自動対応
- 製造・開発現場:作業マニュアルや過去の不具合対応記録の検索
- 営業部門:過去提案の事例検索、製品知識の即時共有
- 法務・コンプライアンス:契約書や法的ガイドラインの照会、社内規程の検索
- 新人教育:基本的な業務ナレッジの即時アクセスによるOJT負担の軽減
- RAGによる情報の信頼性は担保されますか?
RAGは検索元となった文書の出典を明示できるため、生成AIの回答に対する信頼性を担保できます。利用者は出典を確認しながら判断できるため、誤解や誤用のリスクを回避することも可能です。
まとめ
LLMとRAGの組み合わせは、業務の属人化という根深い課題を解決し、社内に眠る知識を有効活用するための強力なナレッジマネジメント基盤を提供します。単なる業務効率化にとどまらず、情報の信頼性を担保しながら知の共有・活用・蓄積を促進することで、組織全体の意思決定力や学習力を高める戦略的な武器となります。
この仕組みを自社で実現するためには、まず社内のどのような情報が、どこに、どのような形で存在しているかを把握することが第一歩となります。しかし、散在するデータを整理し、自社の業務に最適な形でAIが活用できるシステムを構築するには専門的な知見が不可欠です。
もし具体的な導入計画や、現状の課題整理から専門家のアドバイスが必要であれば、ぜひ一度ご相談ください。

AI Market 運営、BizTech株式会社 代表取締役|2021年にサービス提供を開始したAI Marketのコンサルタントとしても、お客様に寄り添いながら、現場のお客様の課題ヒアリングや企業のご紹介を5年以上実施しています。これまでにLLM・RAGを始め、画像認識、データ分析等、1,000件を超える様々なAI導入相談に対応。AI Marketの記事では、AIに関する情報をわかりやすくお伝えしています。
AI Market 公式𝕏:@AIMarket_jp
Youtubeチャンネル:@aimarket_channel
TikTok:@aimarket_jp
運営会社:BizTech株式会社
掲載記事に関するご意見・ご相談はこちら:ai-market-contents@biz-t.jp

