製造業でAIエージェントは使える?機能・主なサービス・注意点を徹底紹介!
最終更新日:2026年01月12日
記事監修者:森下 佳宏|BizTech株式会社 代表取締役
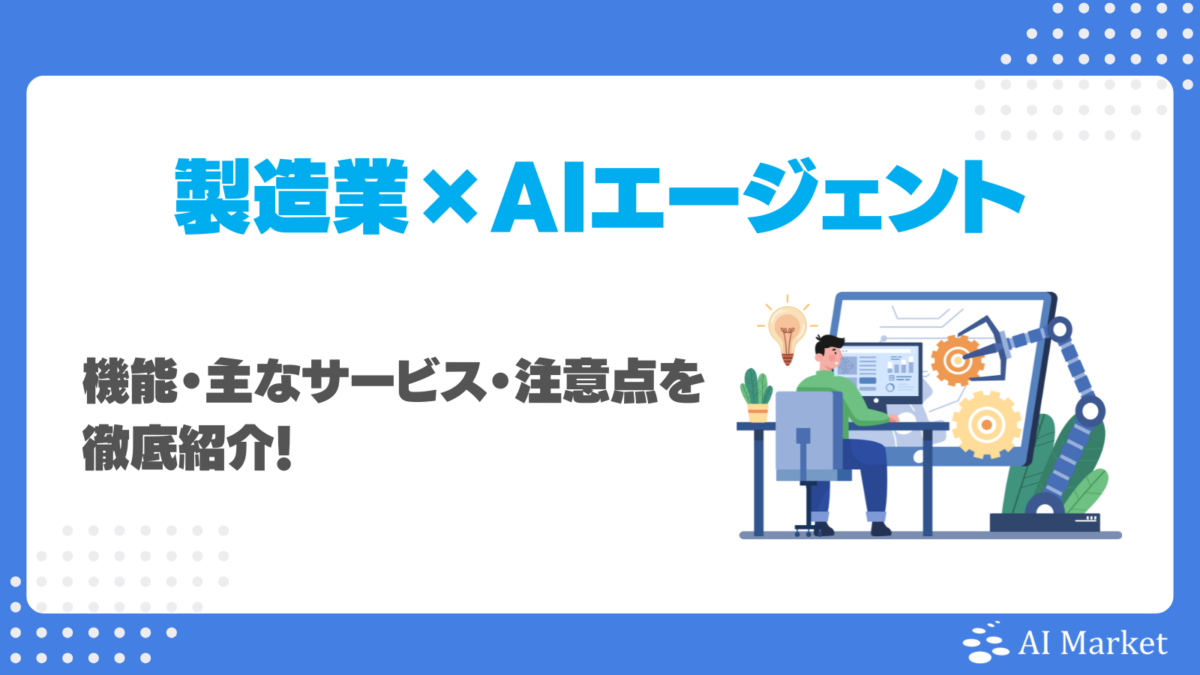
- LLM(推論)、IoT(知覚)、デジタルツイン(検証)が融合したことで製造現場の不確実性やリアルタイム性に対応可能なAIエージェントが実現
- 異常検知から原因特定、復旧案の立案・検証までを自律的に実行する「エージェント」機能
- 予知保全、サプライチェーン最適化、技能伝承といった経営課題に対して従来の人手依存からの脱却が可能に
- 既存システム(ERP等)との連携、学習データの品質確保(マニュアル整備等)といった、ITとOT(制御技術)を統合する環境整備が不可欠
「AIエージェントはチャットボットの延長であり、ホワイトカラーの業務効率化ツールである」。そうお考えの方もまだまだ多いのではないでしょうか?
確かに以前の技術では、物理的な実体があり、かつ厳密なコントロールが求められる製造現場への適用は困難でした。しかし、最新の「AIエージェント」は、単なる自動化ツールではなく、熟練エンジニアのように状況を観察し、思考し、検証した上でアクションを起こすパートナーへと進化しています。
本記事では、製造業におけるAIエージェントシステムの主な機能や導入メリット、サービス例、活用事例、導入におけるリスク管理を紹介します。
AIエージェントに強い会社の選定・紹介を行います
今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
完全無料・最短1日でご紹介 AIエージェントに強い会社選定を依頼
目次
製造業でAIエージェントは使えない?

ルールベースの自動化が行き渡った製造現場において、AIエージェント導入の障壁となっていたのは現場特有の「不確実性」と「リアルタイム性」への対応でした。
しかし現在、この壁は取り払われつつあります。転換点は、高度な推論能力を持つLLMと、現場をデータ化するIIoT、そしてリスクフリーな検証環境であるデジタルツインの融合です。
これらがどのように連携し、従来のFA(ファクトリーオートメーション)の限界を超えていくのか、そのメカニズムを解説します。
LLM: ルールベースを超えた文脈理解と柔軟な判断
AIエージェントが製造業で本格的に活用できるようになった大きな転換点が、LLM(大規模言語モデル)の登場です。
従来の製造現場では、設備の稼働条件や生産スケジュール、異常時の対応など、複雑かつ高度な判断を要する業務は人間がルールベースに基づき対応する必要がありました。
しかし、従来のルールベース型AIや一般的な生産管理システムは、ルール外のケースへの対応や文脈をまたぐ複雑な指示の意図解釈ができませんでした。
一方、LLMを搭載したAIエージェントは曖昧な指示から意図を汲み取り、状況に合わせてタスクを分解・計画(Planning)する能力を持っています。これにより、「異常値を検知したら即停止」だけでなく、「文脈を判断してパラメータを微調整し、稼働を維持する」といった人間のような柔軟な判断が可能になりました。
AIエージェントは現場の自律的な意思決定支援や状況に応じた柔軟な対応ができ、従来自動化が難しかった幅広い製造分野での活用が進んでいます。
IoT/IIoT:AIに物理世界の目と耳を与える
かつて、どれほど優れたアルゴリズムのAIがあっても、現場のデータが紙やオフラインのPLCに閉じていては何もできませんでした。オフィス業務と異なり、物理世界への介入には「現在の状況」を正確に把握する知覚能力が不可欠だからです。
しかし、IoT(Industrial Internet of Things=モノのインターネット)やIIoT(Industrial Internet of Things=産業分野に特化したIoT)の発展によって状況は一変しました。工場内のあらゆる設備やセンサーがネットワーク化され、温度や、稼働率ライン速度など、膨大なデータをリアルタイムで収集できるようになったのです。
その結果、AIエージェントはIoTやIIoTから得られる大量のデータを、現場やシステムを観察するための情報源として活用できるようになりました。IoT以前では不可能だった常時監視・リアルタイム判断が実現し、AIエージェントの有効活用が可能となったのです。
デジタルツイン::無限のシミュレーション環境
「AIが誤った判断をして設備を壊したらどうするのか?」という製造業最大の懸念に対する回答がデジタルツインです。デジタルツインとは、現実の工場や設備を仮想空間上に再現し、実際の挙動をシミュレーションできる技術です。
生成AIによるコード生成や判断には、ハルシネーション(誤り)のリスクが伴います。しかし、AIエージェントは製造業でのデジタルツインに仮想環境を活用し、現実の生産ラインに影響を与えることなく、数千回規模のシミュレーションを安全に実行できます。
そのため、最適な工程設計や生産スケジュール、異常時の対応策を事前に検証でき、現場でのリスクを最小化できます。
特に、自動車や半導体など精密な工程管理が求められる業界では、デジタルツインとAIエージェントの組み合わせが品質安定とコスト削減の両立に欠かせません。
エージェンティックAI:受動的AIから能動的エージェントへ
これまでのAI(チャットボットや画像検査AI)と、AIエージェントの決定的な違いは実行能力にあります。
従来のAI(Copilot型など)では、「このPLCコードのバグを見つけて」と頼むと修正案を提示してくれます。そのあとは、人間がコードをコピペして適用する必要があります。
一方、AIエージェントは「ラインAの稼働率が低下している。原因を特定して復旧案を実行せよ」という指示に対し、自らログサーバーにアクセスし、エラーを特定します。そして、パラメータ修正案を作成し、シミュレータで検証まで行ってから人間に承認を求めるのです。
つまり、AIエージェントは「Perception(認識)→ Brain(計画・推論)→ Action(ツール操作)」というループを自律的に回すことができます。これは、熟練エンジニアが頭の中で行っているトラブルシューティングや設計プロセスそのものを模倣する技術です。
AIエージェントに強い会社の選定・紹介を行います 今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え! ・ご相談からご紹介まで完全無料 完全無料・最短1日でご紹介 AIエージェントに強い会社選定を依頼
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
製造業向けAIエージェントでできることは?
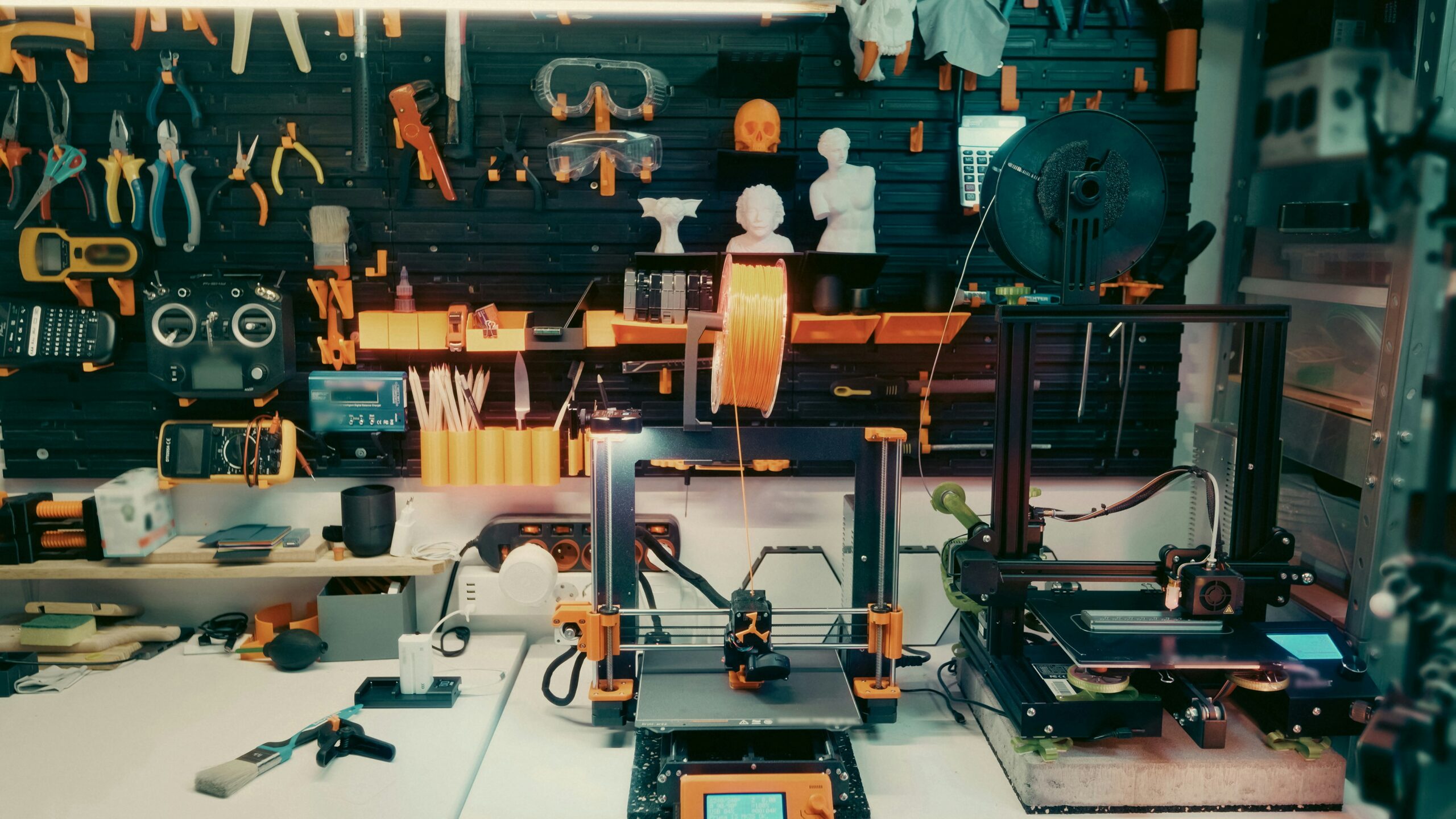
本章では、製造業向けAIエージェントの主な機能を紹介します。
異常検知時のアラート、メンテ指示
製造業向けAIエージェントの代表的な機能の一つが、異常検知時の自動アラートとメンテナンス指示です。
AIエージェントは、IoTセンサーや機器ログから取得したデータを常時監視し、振動・温度・圧力・電流値などの異常パターンをリアルタイムで検出します。
異常検知の一連の流れを人間の判断を待つことなく、AIが即座に「どの設備で、どのような異常が起きているか」を分析し、担当者へ通知します。
また高度なAIエージェントでは、異常検出後に自動で原因分析や対処指示を行うことも可能です。例えば、以下のように判断から指示出しまでを一貫して自律的に実行します。
- モーター温度上昇
- 軸受け摩耗の可能性
- 部品交換を推奨
このような機能により、ダウンタイムの削減や保守作業の効率化、現場担当者の負担軽減が実現し、全体の稼働率向上につながります。
サプライチェーンのリアルタイム最適化
AIエージェントは、製造現場内だけでなく、調達・生産・出荷を含むサプライチェーン全体の最適化にも活用可能です。
従来、人手で調整していた生産計画や在庫補充、納期管理などをAIエージェントはリアルタイムデータをもとに自動で再計算・最適化します。例えば、部品の納入遅延や急な注文変更が発生した際にAIエージェントが即座に代替ルートを提案し、生産ラインの停止を防ぎます。
AIエージェントを活用することで、サプライチェーンを静的な管理から動的で自律的な最適化へと発展させられます。
エンジニアリング・設計支援
AIエージェントは、市場動向や競合製品のデータを自動収集・分析し、新製品企画や改良設計における意思決定のサポートが可能です。
デジタルツイン技術と組み合わせることで、現実の製品や生産ラインを仮想空間上に再現し、AIが数千回規模のシミュレーションを実行することが可能になりました。例えば、AIエージェントが仮想環境内で設計変更を繰り返し、最もコスト効率が高く品質も安定する製造条件を導き出せます。
また、シミュレーション結果を自動で分析・レポート化し、従来は数週間かかっていた検証作業を数時間単位に短縮することも可能です。
ナレッジ共有
AIエージェントは、熟練者の経験やノウハウを蓄積するための現場向けナレッジ共有プラットフォームとしても機能します。
例えば、現場で発生したトラブルや改善事例、作業手順書などをAIが自動で整理・分類し、即座に過去データやマニュアルから最適な回答を提示します。ユーザーが専門用語を使わずとも、自然文で回答を得られる点がメリットです。
また、AIエージェントが日々の対話や問い合わせ履歴を学習することで回答精度が継続的に向上し、熟練者が直接指導しているような環境を実現できます。
最新技術情報の収集
AIエージェントは、特許情報や論文、技術動向を解析することで開発テーマの方向性や市場機会を可視化し、IP戦略を推進します。
特に注目されているのが特許情報を活用した市場・技術分析です。AIエージェントが世界中の特許データを自動収集・分析することで、「どの企業がどの分野に注力しているか」「どの技術が成長しているか」を俯瞰的に把握できます。
その結果、自社の技術ポジションを明確化し、将来の研究開発テーマ設定にも活かせます。
知的財産の防衛
また、AIエージェントは特許侵害リスクの軽減にも役立ちます。特許公開情報を定期的にモニタリングし、類似技術や出願動向を検知することで潜在的な侵害リスクを早期に発見します。必要に応じて警告や回避策の提案を自動的に行うことも可能です。
さらに、競合他社の特許・開発事例の自動調査にも対応し、研究者や知財担当者のリサーチ工数を削減します。従来は人手に頼っていた分析・比較業務をAIが代行し、迅速かつ戦略的な知財判断が実現します。
製造現場でAIエージェントを活用するメリット
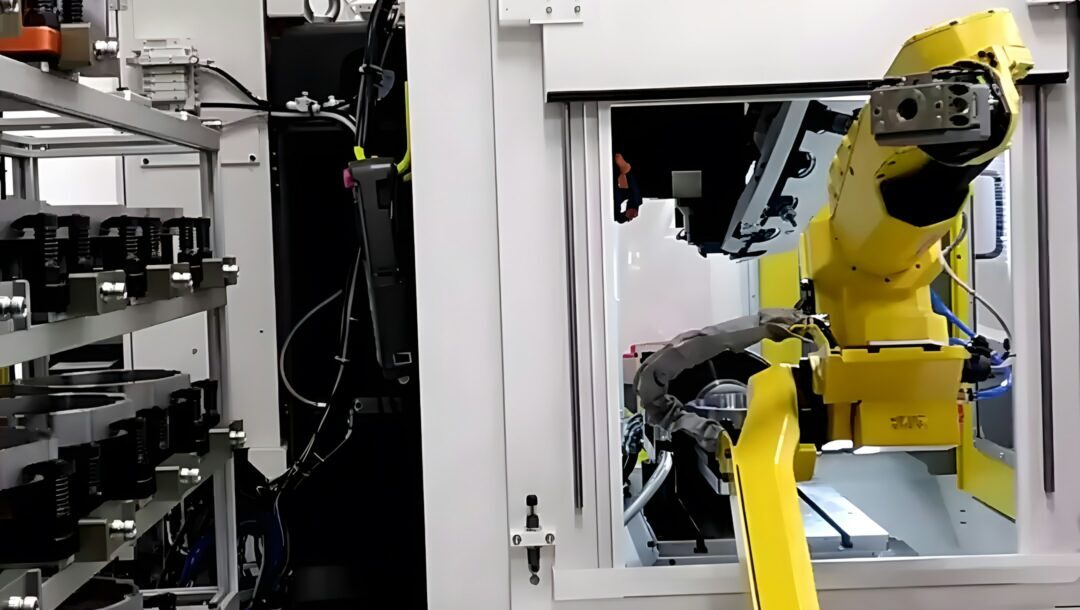
本章では、製造現場でAIエージェントを活用するメリットを紹介します。
技能伝承の効率化
AIエージェントを活用することで、熟練者の経験や判断プロセスをデータとして蓄積・再利用が可能です。
例えば、過去の生産データや作業ログ、トラブル対応履歴をAIが分析し、最適な作業手順や判断基準を自動で提示します。そのため、新人従業員はチャットや音声対話でAIエージェントに質問するだけで熟練者の知見を即座に参照できます。
また、AIエージェントは新入社員や若手スタッフの教育支援ツールとしても有効です。例えば、エラー時にリアルタイムで改善提案を行えるため、OJTの効率化や教育コストの削減を実現します。
人手不足の解消
人手不足が深刻化する製造業では、AIエージェントの導入が労働力の補完・自動化に効果的です。
AIエージェントは、スケジュール調整や品質検査データの分析、報告書作成など、手間と時間がかかる管理・判断業務を自動化します。その結果、限られた人材をより価値の高い業務に集中させられます。
また、AIエージェントは24時間稼働可能なため、夜間監視や遠隔オペレーションにも対応可能です。設備の稼働状況を常時モニタリングし、異常時には自動通知や一次対応を行うことで人手不足による監視漏れ・遅延リスクを低減します。
AIエージェントの導入により、現場の省人化・自動化が進み、少人数でも安定した生産体制を維持できるようになります。特に中小製造業においては、労働力不足を補う有効なソリューションとして有効です。
品質の安定化
AIエージェントを導入すると、製造現場における品質のばらつきを最小限に抑えられます。
AIエージェントは生産データや検査データをリアルタイムで分析し、微細な異常やトレンド変化を人間より早く検出します。その結果、不良品の発生を未然に防止し、安定した品質を維持できます。
また、AIエージェントは過去の製造条件と品質結果を学習し、最も高品質な状態を自動で再現することが可能です。そのため、熟練者の勘や経験に頼らない、データドリブンな品質管理が実現します。
結果として、製造プロセス全体のばらつきが減少し、一定レベル以上の品質を常に確保できる体制が整います。
業務効率の向上
AIエージェントは、日々の生産計画や在庫管理、検査報告などの定型業務を自動化し、製造現場の業務効率を向上させます。
例えば、生産スケジュールの調整や作業指示書の生成をAIエージェントが自動で行うことで、プロジェクト管理を行うPMの負担を削減します。また、異常検知や設備保守の提案もAIエージェントが自律的に実行するため、人間の判断や報告待ちによるタイムロスの削減も可能です。
その結果、AIエージェントの活用により、製造プロセス全体のリードタイム短縮や生産ラインの稼働率向上が実現します。
現場の意思決定スピード向上
従来製造現場の意思決定では、データ収集から分析、報告、承認まで複数プロセスを経る必要があり、対応が遅れるケースも少なくありませんでした。
その点、AIエージェントは意思決定に必要な全工程を自動化し、現場で即座に判断できる環境を構築します。
例えば、生産ラインで異常が検出された場合、AIがその原因と影響範囲を瞬時に特定し、最適な対応案を提示します。PMはその場で判断・実行できるため、ダウンタイムを最小化できます。
また、AIエージェントが経営層や他部署と情報を連携すると、部門間の意思決定もスムーズになる点もメリットです。
AIエージェントは、生産現場で収集したデータを自動で整理し、経営層・品質管理部門・生産管理部門など各部門が必要とする形に加工して共有できます。その結果、「現場の状況が見えない」「判断材料が不足している」などの情報格差が解消され、部門横断での判断スピードが大幅に向上します。
AIエージェントに強い会社の選定・紹介を行います 今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え! ・ご相談からご紹介まで完全無料 完全無料・最短1日でご紹介 AIエージェントに強い会社選定を依頼
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
製造業向けAIエージェントサービス例
本章では、製造業向けに提供されるAIエージェントサービスの例を紹介します。
NECのAIエージェント

日本電気株式会社(NEC)のAIエージェントは、NEC独自の生成AI「cotomi(コトミ)」が 自律的にタスクを分解し、業務プロセスを自動設計・実行するサービスです。
以下が主な特徴です。
- 実現したい業務を入力すると、目的を解析し、必要タスクを自律的に分解
- タスク内容に応じて、複数のAIツールを組み合わせて最適なワークフローを実現
- 社内データと外部情報を包括的に収集し、分析結果を踏まえて資料や計画書などの成果物を生成
例えば、「キャリア採用者の育成戦略を作りたい」と入力した場合、cotomiは最終成果物を育成計画書と判断し、情報収集・分析・プログラム策定などのタスクを自動で構築します。それぞれのタスクに適したAIを選び、プロセス全体を統合して育成計画書を完成させます。
NECのAIエージェントは、社内外の情報を包括的に検索し、意思決定プロセスを自動化できる点が強みです。
Siemens Industrial Copilot
Siemens Industrial Copilotは、シーメンスのデジタルビジネスプラットフォーム「Siemens Xcelerator」に蓄積されたオートメーション情報とプロセスシミュレーションデータを基盤に、Microsoft Azure OpenAI ServiceのLLMを組み合わせて構築されたAIエージェントです。
Industrial CopilotはTIAポータルとのシームレスな連携により、エンジニアリング業務を以下のように支援します。
- SCLコードの自動生成・文書化サポート:自然言語での指示からSCLコードを生成し、必要なドキュメントも自動で作成
- WinCC Unifiedの画面生成・調整の自動化:HMI/SCADAのビジュアライゼーション画面をAIが生成し、仕様に基づいて自動調整
- 自然言語によるドキュメント検索の高速化:複雑な技術文書も、質問を自然言語で入力するだけで検索・要約が可能に
セキュリティ・データ保護・信頼性を重視した設計により、製造現場でも安心して活用できる点が特徴です。Industrial Copilotを活用することで、開発業務の品質とスピードを向上させられます。
General Electricの産業用AIエージェント

General Electric社(GE)は、製造業やエネルギー産業の設備予知保全・運用最適化・品質管理を支援する高度な産業用AIエージェントを提供しています。
GEのAIエージェントは、同社のプラットフォームである「Predix」と「APM(Asset Performance Management)」に統合されています。
以下が、主な特徴です。
- IoTセンサーから収集した温度・振動・圧力・負荷などのデータを解析し、故障の兆候を早期に検知
- 設備の劣化傾向、稼働履歴、環境条件を学習し、最適な点検タイミングや交換部品を提案
- 過去データとリアルタイムデータを組み合わせて、製造ラインや発電設備の最適なパラメーターを提示
- 設備近くで即時処理が必要なケースはエッジで、広域の統合管理が必要な場合はクラウドなど現場環境に応じた運用に対応
GEの産業用AIエージェントは、同社が長年蓄積してきた産業機器の知見とデータ分析技術を基盤とし、現場オペレーションの高度化と安定稼働を実現します。
製造現場へAIエージェントを導入する際の注意点

AIエージェントの導入を成功させるためには、システム選定やデータ管理、運用体制などにおいて、いくつか注意点があります。本章では、製造現場へAIエージェントを導入する際の注意点を紹介します。
連携性を重視したAIエージェントシステムの選定
製造現場にAIエージェントを導入する際は、既存システムとの連携性を最優先で確認することが重要です。
AIエージェントは単独ではなく、品質管理システムやERPなど複数の業務システムと連携してこそ効果を発揮するためです。例えば、ERPとリアルタイムにデータを共有することで生産計画の変更や在庫調整を自動で反映し、現場の意思決定スピードを高められます。
以下が、具体的な選定ポイントです。
- APIやデータフォーマットの互換性が高く、将来的な拡張にも対応
- リアルタイムでの情報共有や双方向通信が可能なアーキテクチャを採用
- 異なるベンダー製システムとの相互運用性が確保されている
- データ連携のセキュリティ要件を満たしている
これらのポイントを満たすシステムを選定することで、既存システムを生かしつつスムーズに導入でき、現場の高精度な意思決定が実現します。
データの整備
AIエージェントの性能を最大限に引き出すには、現場データの整備が欠かせません。AIエージェントは過去の作業記録や製品マニュアルなどを参照して回答や判断を行うため、入力データの品質がそのまま出力結果の精度を左右します。
そのため、導入前に以下の整備が重要です。
- 属人化された情報を文章化・体系化して、検索しやすい形式にする
- 古い手順書・マニュアルのアップデートを行い、最新の業務フローと整合させる
- ログデータやセンサー情報のタグ付け・構造化により、AIが文脈を正しく理解できるようにする
データが古い場合や誤った情報が多い場合はAIが誤った判断を下すため、導入前にデータ品質を確保しておくことがAIエージェントの精度・信頼性を担保するうえで不可欠です。
現場が継続的に使える運用体制の設計
AIエージェントの費用対効果を高めるためには、現場で日常的に使われ、継続的に改善される運用体制を整える必要があります。導入初期は注目されても、評価・改善サイクルがないと、すぐに活用されなくなります。
継続的に活用するためには、以下のような役割別の運用フロー設計が重要です。
| 役割 | 主なタスク |
|---|---|
| データ管理担当 | マニュアル・保守記録・ナレッジデータを常に最新状態に更新し、AIの回答精度を維持 |
| 現場リーダー | 現場からのフィードバックや改善要望を定期的に収集し、AI運用チームに共有 |
| AI運用担当 | モデルやRAG(検索拡張生成)の精度評価を行い、チューニングやデータ追加を実施 |
タスクを分担することで、利用状況の把握からデータ更新、モデルの精度向上が継続的に循環する体制を構築でき、AIエージェントを長期的に安定運用できます。
セキュリティ・情報管理ポリシーの明確化
AIエージェントの導入にあたっては、セキュリティや情報管理のポリシーを導入前に明確化することが不可欠です。
AIエージェントは製造データや設備データなど機密情報へ常時アクセスする仕組みであり、管理ルールが曖昧なまま運用を始めると、情報漏えいや不正利用のリスクが高まるためです。
また、従来のシステムよりも扱うデータ量が大きく、外部サービスと連携するケースも増えます。そのため、早期に統一ルールを整備しておかないと事故発生時の原因特定が難しくなるリスクもあります。
以下が、具体的なポイントです。
- データ保存先:社内サーバーかクラウドかを明確にし、リスクとコストのバランスを検討
- 権限管理:部署・役職ごとにアクセス権を細かく設定し、閲覧・編集可能範囲を明確化
- 操作ログ追跡:誰が・いつ・どの情報にアクセスしたかを自動で記録し、不正利用の早期検知に活用
これらを事前に整備しておくことで、セキュアなAIエージェントのシステム環境を構築できます。
AIエージェントに強い会社の選定・紹介を行います 今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え! ・ご相談からご紹介まで完全無料 完全無料・最短1日でご紹介 AIエージェントに強い会社選定を依頼
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
製造業におけるAIエージェント活用についてよくある質問まとめ
- AIエージェントは既存の生産管理システム(ERP/MES)と連携できますか?
主要ベンダーのAIエージェントはAPI連携に対応しており、多くのシステムと接続可能です。
導入前に連携性を必ず確認することが重要です。
- 製造現場でAIエージェントを使うとセキュリティは大丈夫ですか?
クラウド・オンプレに応じた対策、アクセス権限管理、操作ログの取得を徹底することで安全に運用できます。
製造データの扱いは導入前にポリシーを明確化する必要があります。
- AIエージェントは製造業で具体的に何ができますか?
主に以下の領域で「自律的な」業務遂行が可能です。
- 異常検知・保全: 予兆の検知から原因特定、メンテナンス指示までを自動化。
- サプライチェーン最適化: 納期遅延時の代替ルート提案や在庫調整。
- エンジニアリング支援: 製品設計のシミュレーションや制御コードの生成。
- ナレッジ共有・技術調査: 熟練工のノウハウ検索や、特許・技術情報の自動収集。
まとめ
AIエージェントは、異常検知時のアラートやサプライチェーンのリアルタイム最適化など、製造現場の幅広い業務を自動化し、製造現場の人手不足解消や業務効率向上を実現します。
近年は、LLM・IoT・デジタルツイン技術の発展により、従来は自動化が難しかった高度な判断業務にも対応可能となり、多くの製造企業で実用化が進みつつあります。
一方、効果を最大化するには、データ整備や運用体制の構築が欠かせません。これらを適切に整えることで、AIエージェントは現場に定着し、長期的な価値をもたらします。
自社の課題に対して、どの領域からAIエージェントを適用すべきか、また既存データをどう活用すべきか検討される際は専門的な知見を持つパートナーへの相談が近道です。まずは現状の課題整理から始めてみてはいかがでしょうか。

AI Market 運営、BizTech株式会社 代表取締役|2021年にサービス提供を開始したAI Marketのコンサルタントとしても、お客様に寄り添いながら、現場のお客様の課題ヒアリングや企業のご紹介を5年以上実施しています。これまでにLLM・RAGを始め、画像認識、データ分析等、1,000件を超える様々なAI導入相談に対応。AI Marketの記事では、AIに関する情報をわかりやすくお伝えしています。
AI Market 公式𝕏:@AIMarket_jp
Youtubeチャンネル:@aimarket_channel
TikTok:@aimarket_jp
運営会社:BizTech株式会社
掲載記事に関するご意見・ご相談はこちら:ai-market-contents@biz-t.jp

