エージェンティックAI(エージェント型AI)とは?AIエージェントとの違い・重要技術・導入するためのプラットフォーム・注意点を解説!
最終更新日:2025年12月09日
記事監修者:森下 佳宏|BizTech株式会社 代表取締役
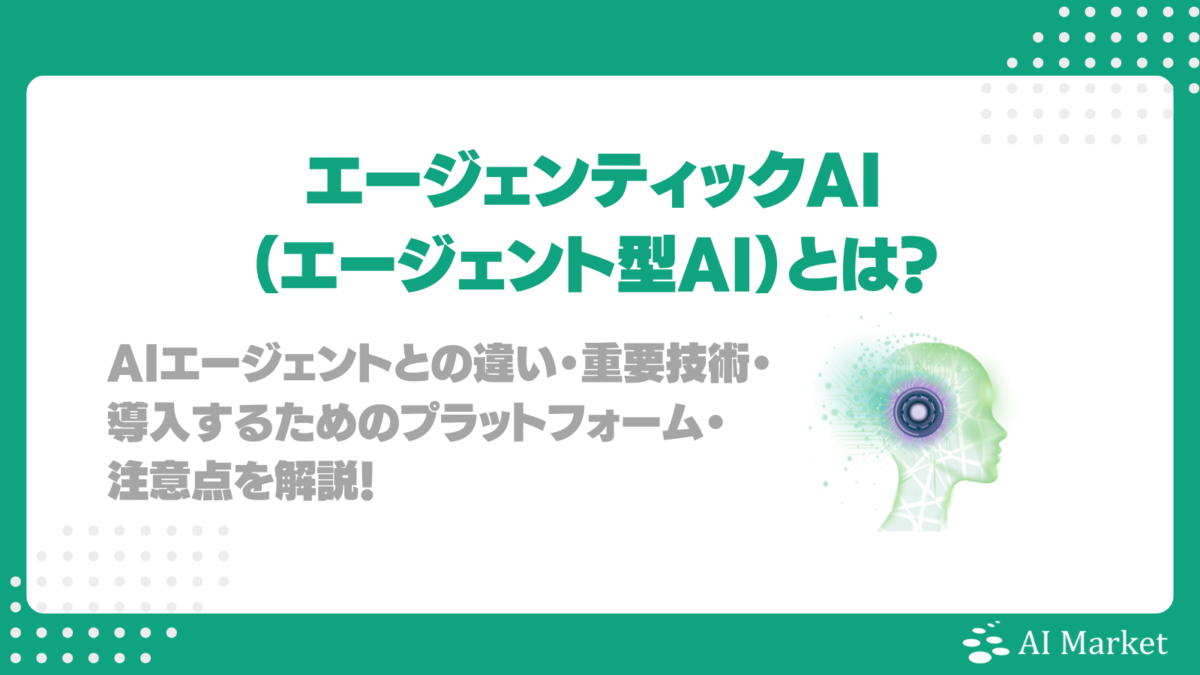
- エージェンティックAIは、特定のツールの名称ではなく、AI自身が計画・実行・自己修正を繰り返して自律的に目的を達成する「設計思想」
- 実装には「ReAct(思考と行動のループ)」や「マルチエージェント構成」の理解が不可欠
- 導入にはDifyのようなローコードツールから、AWS/Google等のクラウド基盤、LangGraph等のコードベースまで多様な選択肢
生成AIのトレンドは今、単なる質問応答から、自律的にタスクを完遂する「エージェンティックAI(Agentic AI)」へと移行しています。エージェント型AIとは、AIが自ら状況を判断し、計画を立ててタスクを進める自律型AIです。
本記事では、エージェンティックAIの本質的な定義、AIエージェントとの違い、知っておくべき技術的裏側(ReAct、マルチエージェント)、そして具体的な開発フレームワークまでを体系的に解説します。
AIエージェントに強い会社の選定・紹介を行います
今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
完全無料・最短1日でご紹介 AIエージェントに強い会社選定を依頼
目次
エージェンティックAI(エージェント型AI)とは?

エージェンティックAI(エージェント型AI:Agentic AI)とは、AI自身が目的を理解し、その達成に必要な手順(タスク分解・実行・改善)を自律的に考え、実行する「振る舞い」や「システム設計のアプローチ」を指す言葉です。
ChatGPTなどのLLM(大規模言語モデル)の登場により、AIは高度な「脳(思考力)」を手に入れました。しかし、それだけでは現実世界の仕事は完結しません。
AIに「手足(ツール利用)」と「自律性(計画と実行)」を与え、実社会でタスクを完遂できるようにする技術こそがエージェンティックAIです。
これまでのAIが、人間が都度指示を出す「道具(Tool)」だったのに対し、エージェンティックAIは人間に代わって行動する「代行者(Agent)」としての性質を強く持っています。
エージェンティックAIとAIエージェントの違い
多くの人が混乱するのが「AIエージェント」との違いですが、これは「実体」と「性質」の違いと捉えると本質が見えてきます。AIエージェント(名詞)は仕組み・ソフトウェアの実体を指します。
一方、従来のAIエージェント(単なる自動化ツール)を、もっと自律的(エージェンティック)に振る舞えるように進化したものであり、「AIエージェント(実体)」を、より「エージェンティック(自律的)」に動かすための最新技術や設計思想がエージェンティックAIとも言えます。
従来の単純なチャットボットやコパイロット(Copilot)も、AIを搭載していれば広義には「AIエージェント」です。しかし、エージェンティックAIは、壁にぶつかった際に「別の方法を試そう」と自己修正(Reflection)する能力を持つ点が決定的に異なります。
AIエージェントに強い会社の選定・紹介を行います
今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
完全無料・最短1日でご紹介 AIエージェントに強い会社選定を依頼
エージェンティックAIを実現するための技術

エージェンティックAIの実装について議論する際、裏側でどのような処理が走っているかを理解するために以下の3つの技術概念を押さえておきましょう。
思考と行動のループ(ReAct / CoT)
「ReAct(リアクト)」とは、Reasoning(推論)とActing(行動)を組み合わせたプロンプトエンジニアリングの手法です。従来のチャットボットが「質問→回答」の1往復で終わるのに対し、エージェンティックAIは以下のようなループを内部で回しています。
- Thought(思考): ユーザーの目的を達成するには、まず在庫データが必要だ。
- Action(行動): 在庫確認APIを叩く。
- Observation(観察): APIから「在庫あり:5個」という結果が返ってきた。
- Thought(再考): 在庫はある。次は配送日を確認する必要がある…
ただし、ループが回るたびにAPI利用料(トークン課金)が発生し、待ち時間も増えます。そのため、最大ループ回数(Loop Limit)や無限ループに入った時の処理は検討が必要です。
ツール利用(Function Calling / Tool Use)
LLM単体はただの「言葉を知っている計算機」ですが、それに「手足」を与える技術がFunction Calling(ファンクションコーリング)です。
- 検索ツール: Webブラウジングで最新の法改正情報を取得する。
- 計算・分析ツール(Code Interpreter): Pythonコードをその場で書いて実行し、Excelデータを読み込んでグラフを描画する。
- 社内システム連携: SQLを発行してCRMから顧客情報を引き出す。
マルチエージェント・オーケストレーション
エージェンティックAIをシステムに組み込む際、大きく分けて「1つの万能なAIに任せる(シングル)」か、「専門特化した複数のAIを協調させる(マルチ)」かというアーキテクチャの選択があります。
複雑なタスクにおいては「マルチエージェント」が主流になりつつありますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。
以下の表に、両者の違いをまとめました。
| 比較項目 | シングルエージェント構成 (Single-Agent) | マルチエージェント構成 (Multi-Agent / MAS) |
|---|---|---|
| 体制のイメージ | 1人が計画から実行、修正まで全て担当する。 | PM、リサーチャー、エンジニアなど役割分担して連携する。 |
| 技術的特徴 | 1つのLLMがすべてのツール(Web検索、計算など)を使い分ける プロンプトが長くなりやすく、混乱しやすい | 「検索担当」「執筆担当」のようにプロンプト(役割)を分割 各AIのタスクが単純化されるため精度が出やすい |
| メリット |
|
|
| デメリット | タスクが複雑になると途中で目的を忘れたり、指示を取り違える(コンテキスト溢れ)リスクが高い。 |
|
| 適した用途 |
|
|
初期のエージェンティックAIはシングル構成が主流でしたが、「1つのLLMに複雑な指示を与えすぎると性能が落ちる」という課題が浮き彫りになりました。
そこで、人間が組織で働くように、役割を小さく切り出して、専門のエージェント同士に会話させる方が、結果として複雑な問題を高品質に解けることが実証されています。
エージェンティックAIのビジネスにおけるメリット
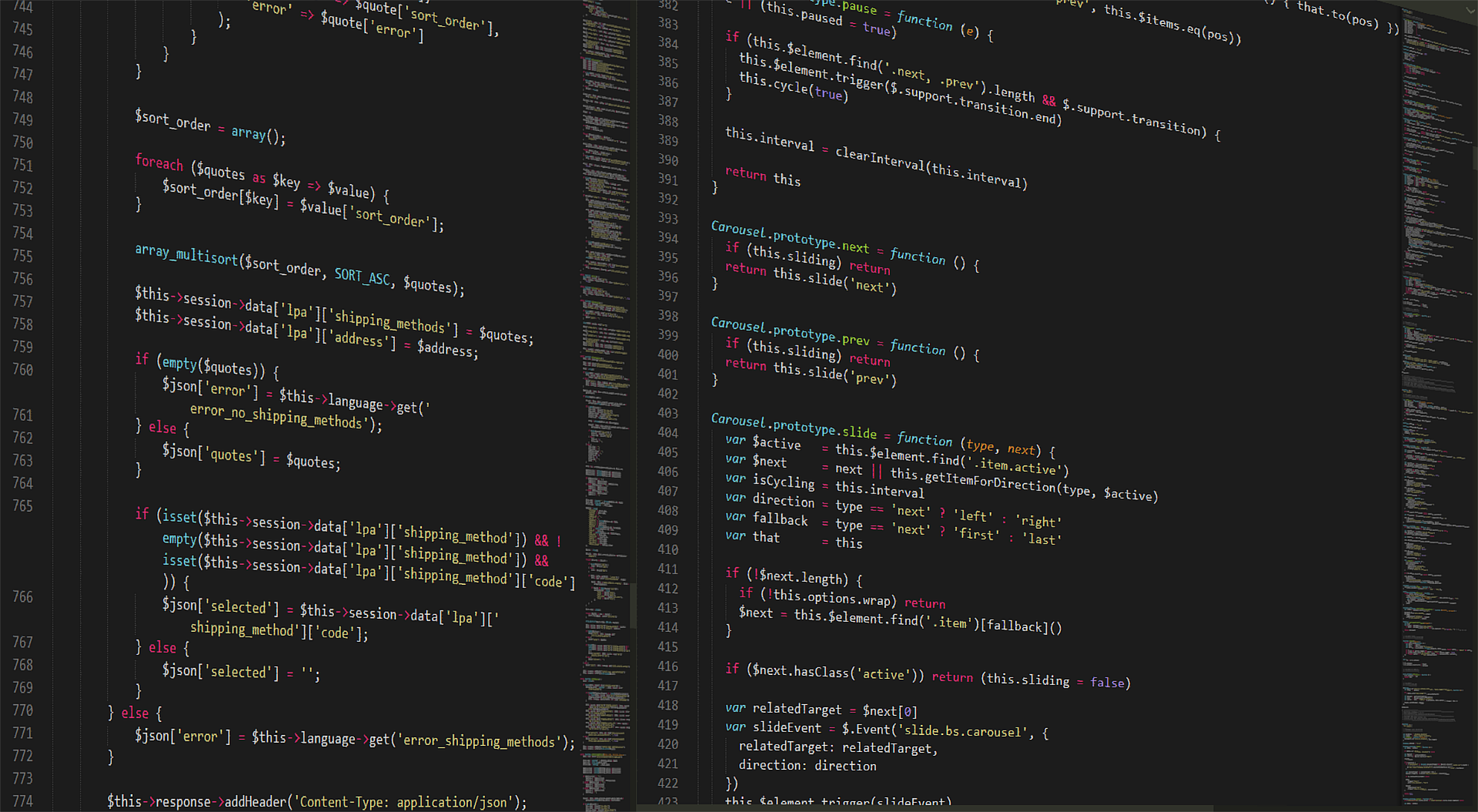
なぜ、単なるLLM(大規模言語モデル)ではなく、あえてコストと開発工数をかけて「エージェンティックAI」を構築するのか。その答えは、AIが提供する価値が「情報の生成」から「業務の完遂」へとシフトする点にあります。
ビジネス実装において、特にインパクトの大きい2つのメリットを深掘りします。
「人間に近い」仕事の任せ方が可能になる
これまでのAI(チャットボット)は、いわば「指示待ちの優秀なアシスタント」でした。的確な回答を得るためには、人間側がタスクを細分化し、一つひとつプロンプトを入力する必要がありました。
エージェンティックAIは、これを「自律的に動く優秀な部下」へと進化させます。
従来(チャットボット)の場合、以下のように人間がずっと画面の前で指示し続ける必要がありました。
- 「A社の競合をリストアップして」→(出力)
- 「それぞれの売上規模を調べて」→(出力)
- 「それを表にまとめて」→(出力)
- 人間がExcelにコピペし、Slackで報告する。
エージェンティックAIの場合、「A社の競合調査を行い、売上比較レポートを作成して、チームのSlackチャンネル(#market-research)にPDFで共有しておいて」と指示すれば十分です。
AIは、指示に基づいて以下のようにプランニングして実行します。
- 計画: 「まずは検索、次にデータ抽出、そしてドキュメント生成、最後にSlack APIへ送信」というプランを策定
- 実行と修正: 検索結果が足りなければ検索ワードを変えて再検索し、目的を達成するまで自走する
- 完了: Slackへ通知が届く。
AIがツール(Webブラウザ、Officeソフト、Slack等)を横断して操作できるため、人間はプロセスの管理から解放され、成果物の評価に集中できるようになります。
幻覚(ハルシネーション)のリスク低減と精度向上
「AIはもっともらしい嘘をつく(ハルシネーション)」という問題は、ビジネス導入における最大の障壁でした。しかし、エージェンティックなワークフローは、このリスクを構造的に低減させます。
従来のLLMが一発勝負(Zero-shot)で回答を出力していたのに対し、エージェンティックAIは、以下のサイクルで内省・自己検証というプロセスを挟むからです。
- Draft(起案): AIが一度答えやコードを作成
- Verify(検証): 別のペルソナを持ったAI(または自身の別ステップ)が、「この情報は事実に即しているか?」「このコードはエラーなく動くか?」をチェック
- Refine(修正): エラーや矛盾が見つかれば自ら修正
例えば、「Pythonでデータ分析をする」タスクにおいて、従来のAIは書いたコードが動かなくてもそのまま提示してきました。しかしエージェンティックAIは裏側でコードを実際に実行し、エラーが出たら修正して再度実行する試行錯誤(トライ&エラー)を繰り返してから、成功した結果だけをユーザーに提示します。
AIエージェントに強い会社の選定・紹介を行います
今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
完全無料・最短1日でご紹介 AIエージェントに強い会社選定を依頼
エージェンティックAIを実現する代表的なサービス・フレームワーク例

エージェント型AIで活用できるサービス・フレームワークには、さまざまなものがあります。
以下では、代表的なサービスを紹介します。
| サービス・ツール名 | 分類 | 特徴 | こんな企業・用途に最適 |
|---|---|---|---|
| Dify | ローコード プラットフォーム | オープンソースのLLMアプリ開発基盤 GUI操作でエージェントやRAGを直感的に構築 日本国内での利用が急増中 | エンジニア不足の企業 社内ツールの開発 PoC |
| AWS Amazon Bedrock Agents | クラウド マネージド | 大手クラウドベンダーの純正機能 セキュリティや権限管理が既存のクラウド基盤と統合されており導入障壁が低い | セキュリティ重視の大企業 既存AWS/Googleユーザー |
| OpenAI Assistants API(Responses API) | API / SDK | ChatGPTと同じモデルをベースに、ツール実行や検索機能をコードから呼び出せる標準的なAPI | 最新のAI性能をフル活用したい 自社プロダクト開発 |
| LangGraph | フレームワーク(Python/JS) | LangChainの拡張版 「条件分岐」や「ループ」など、複雑で厳密な業務フローをコードで記述するのに適する | 複雑な業務ロジックのシステム化 エンジニア主導の開発 |
| crewAI | フレームワーク(Python) | 「リサーチャー」「ライター」のように役割を定義し、チームでタスクをこなす自律的な動きが得意 | 企画、調査、コンテンツ制作などのクリエイティブな自動化 |
| Microsoft AutoGen | フレームワーク(Python) | 複数のエージェント同士が「会話」しながら課題を解決する高度なマルチエージェント基盤 | 研究開発 複雑なコード生成 技術的な難題解決 |
目的に応じて最適なフレームワークを選ぶことで、エージェント型AIの導入効果を最大化できます。構築の容易さ(Dify/クラウド)をとるか、挙動の自由度と制御(LangGraph/AutoGen)をとるかが大きな分岐点になります。
まずはDifyなどでPoC(概念実証)を行い、有効性が確認できてからLangGraphなどで本番開発を行うハイブリッド型のアプローチも有効です。
エージェンティックAI導入に向けた課題とリスク

エージェンティックAIは素晴らしい技術ですが課題も明確です。
無限ループとコスト
AIが「まだタスクが完了していない」と判断し続け、APIを叩き続けたり思考ループに陥ったりすることがあります。これによりAPI利用料(トークンコスト)が青天井になるリスクがあります。
「最大実行回数」の制限や、コスト監視の仕組みが必須です。
レイテンシ(応答速度)
「思考→行動→検証」を繰り返すため、チャットボットのような即答性は失われます。
そのため、リアルタイム性が求められるUI(接客など)には不向きな場合があります。バックオフィス業務向きです。
セキュリティと権限
「メールを送信する」「DBを更新する」といった実行権限を持たせるため、プロンプトインジェクション攻撃(AIを騙して不正な命令を実行させる)のリスクが重大になります。
Human-in-the-loop(実行直前に人間が承認ボタンを押す)の設計が初期段階では推奨されます。
AIエージェントに強い会社の選定・紹介を行います
今年度AI相談急増中!紹介実績1,000件超え!

・ご相談からご紹介まで完全無料
・貴社に最適な会社に手間なく出会える
・AIのプロが貴社の代わりに数社選定
・お客様満足度96.8%超
完全無料・最短1日でご紹介 AIエージェントに強い会社選定を依頼
エージェンティックAI(エージェント型AI)についてよくある質問まとめ
- エージェンティックAI(エージェント型AI)とは何ですか?
AI自身が目的を理解し、タスクの分解・実行・自己修正(Reflection)を行いながら自律的にゴールを目指す「振る舞い」や「システム設計のアプローチ」のことです。従来の指示待ち型AIとは異なり、自ら考え行動する「代行者」としての性質を持ちます。
- エージェンティックAIはどのような技術で実現されていますか?
主に以下の3つの技術要素で構成されています。
- 思考と行動のループ(ReAct): 推論(Reasoning)と行動(Acting)を繰り返し、結果を見て次の行動を決める仕組み。
- ツール利用(Function Calling): Web検索やコード実行、社内DB接続など、外部ツールをAIが自ら操作する機能。
- マルチエージェント: 複数の専門特化したAIが協調して複雑なタスクを解決するアーキテクチャ。
まとめ
エージェンティックAIは、AI活用を「情報の検索」から「業務の代行」へと引き上げ、ハルシネーションのリスクを抑えつつ生産性を劇的に向上させる可能性を秘めています。
しかし、シングルエージェントでスモールスタートすべきか、マルチエージェントで複雑な課題を解くべきか、あるいはどの開発基盤(Dify、AWS、LangGraph等)を採用すべきかといった技術選定は、開発コストやランニングコストに直結する高度な経営判断です。
自社の業務フローに最適なアーキテクチャを設計し、最短距離で成果を出すためには、最新技術に精通した専門家の知見を取り入れたPoC(概念実証)が有効です。まずは実現可能性の診断から始めてみてはいかがでしょうか。

AI Market 運営、BizTech株式会社 代表取締役|2021年にサービス提供を開始したAI Marketのコンサルタントとしても、お客様に寄り添いながら、現場のお客様の課題ヒアリングや企業のご紹介を5年以上実施しています。これまでにLLM・RAGを始め、画像認識、データ分析等、1,000件を超える様々なAI導入相談に対応。AI Marketの記事では、AIに関する情報をわかりやすくお伝えしています。
AI Market 公式𝕏:@AIMarket_jp
Youtubeチャンネル:@aimarket_channel
TikTok:@aimarket_jp
運営会社:BizTech株式会社
掲載記事に関するご意見・ご相談はこちら:ai-market-contents@biz-t.jp

